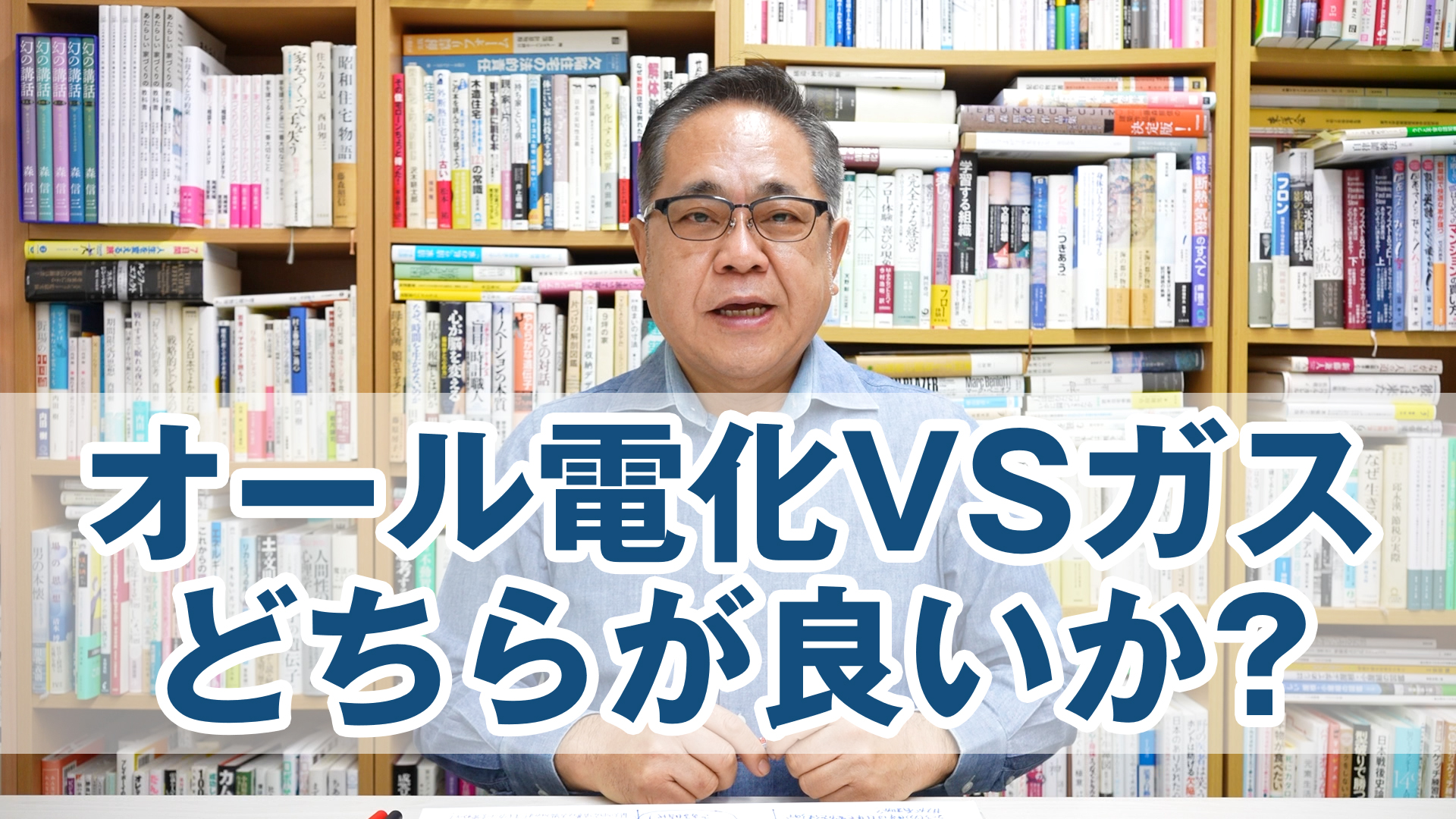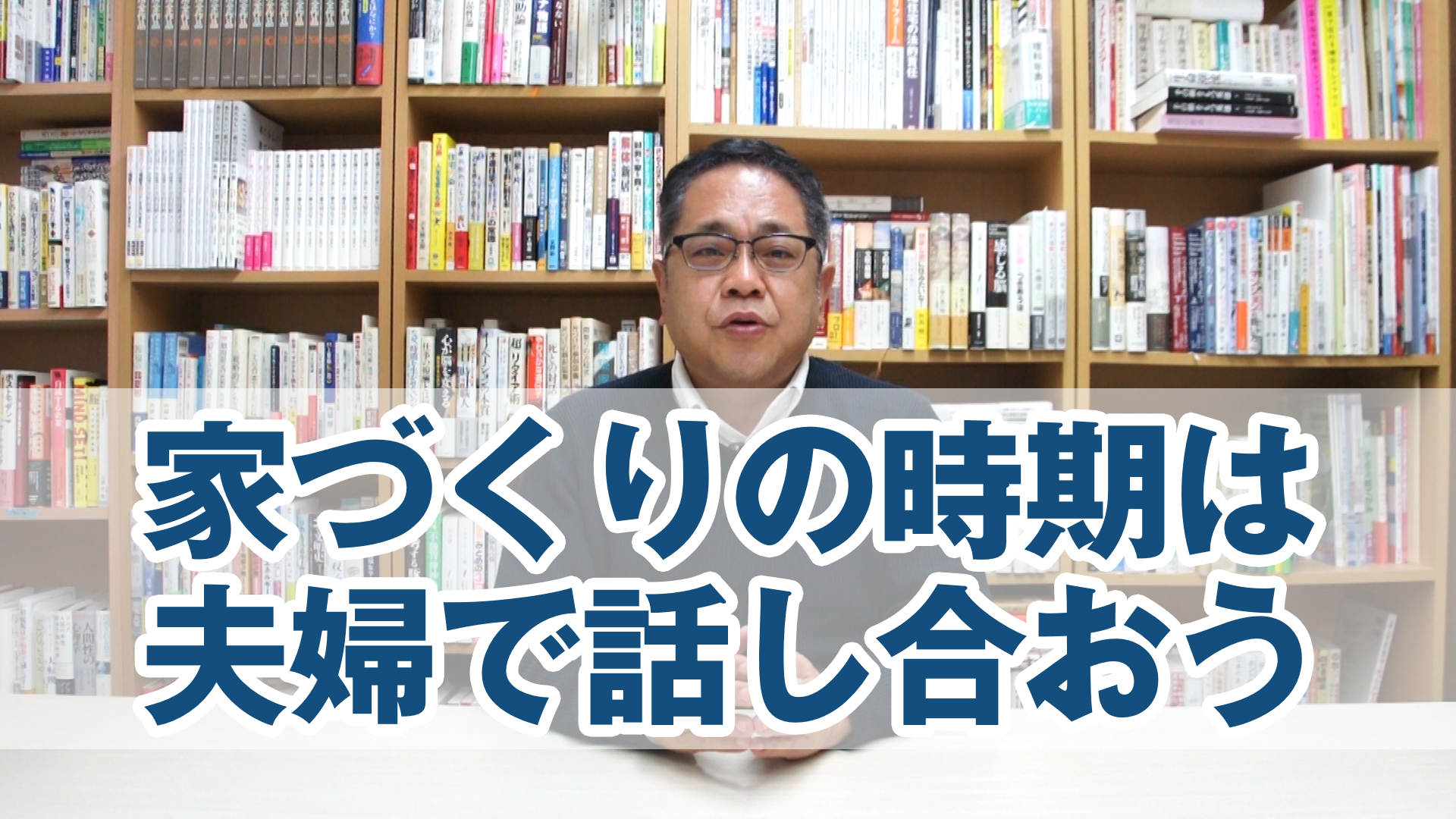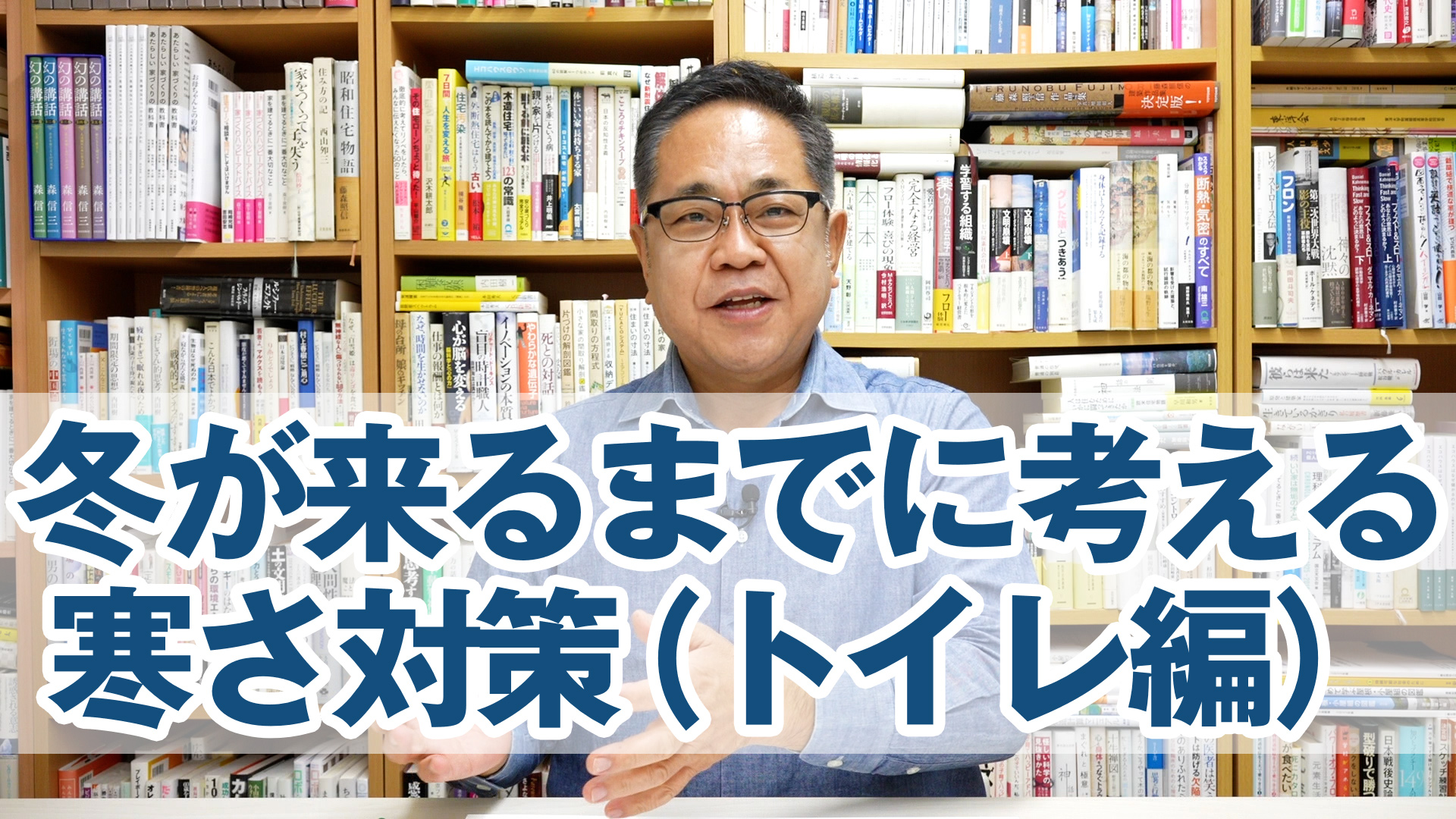相続しないといけない空き家はどうしたらいいのか?
今回は「相続しないといけない空き家はどうしたらいいのか?」について解説します。
みなさんの中には、将来的に相続しなければならない家がある方もいるかもしれません。その家が空き家になりそうな場合、一体どうしたらよいのかと悩むこともあるでしょう。今回は、そうした状況に備えるための予防的な話とともに、すでに問題が目の前にある方にも参考にしていただけるようなお話をしたいと思います。前回の動画でも解説しましたが、現在、空き家に関する法律が変わってきています。前回の動画のリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。
「空き家問題」を考えると見えてくること
https://www.m-athome.co.jp/movie/akiya_mondai_mierukoto
空き家を放置することには、大きなリスクがあります。最近の有名な例として、タレントの松本明子さんが「実家じまい終わらせました」という本を出版されました。また、YouTubeでも関連する動画が公開されています。その内容は、ご両親が亡くなられた後に実家が空き家となり、さまざまな困難や失敗を経験しながらも、何とか処分を終えたというお話です。
空き家をそのまま放置しておく一番の問題は、驚くほど早く老朽化が進むことです。人が住まなくなった家は、あっという間に荒れてしまいます。具体的には、ネズミや近所の猫が住みついたり、鳥の糞で汚れたりすることがあります。そのまま放置すると、そこからさらに荒れていきます。また、庭がある場合、樹木や草が伸び放題になり、道路や隣地にはみ出して近隣に迷惑をかけることもあります。
さらに、空き家だと分かると、不法投棄の対象になることもあります。実際に、長年空き家だった家に浮浪者のような人が勝手に住みついていたことがありました。また、悪意のある人が放火する可能性もあり、大変危険です。もう一つのリスクとして、塀や屋根、外壁が老朽化し、気づかないうちに破損してしまうことがあります。そうした建材が落下し、通行人に怪我をさせるケースもあります。「誰の所有物なのか」「なぜ無管理のまま放置されていたのか」と責任を問われることもあり得るのです。
また、空き家を持ち続ける限り、お金と手間がかかり続けます。手放すまでの数年間、固定資産税を支払い続ける必要がありますし、たまに訪れた際に困るので電気や水道の基本料金も支払わなければなりません。さらに、埃がたまった室内の掃除や庭の草刈りを業者に依頼する維持費もかかります。このように、空き家にはさまざまなリスクが伴います。そのため、空き家になってしまってから困るのではなく、事前にどうするかを考えておくことが大切です。
さらに非常にシビアな話になりますが、空き家を引き継ぐ「相続人」の問題があります。一般的に、相続人は複数いることが多く、兄弟がいる場合などが典型的な例です。このような場合、「遺産分割協議」を行わなければなりません。相続するのは家だけではなく、車や現金など、親御さんが残されたさまざまな財産が含まれます。それらをどう分けるかの話し合いで合意を得なければ、勝手に処分することはできません。
もし遺産分割協議がスムーズに進まなければ、相続をめぐる争いに発展することもあります。そしてこの協議がまとまらないと、空き家は放置されやすくなります。なぜなら、自分のものになるかどうか分からないのに、お金をかけて維持することはできないからです。その結果、相続人同士の話し合いが長引くほど、空き家の放置リスクは高まってしまいます。
もう一つの問題は、親御さんが認知症になってしまうケースです。親が認知症になると、家を売却したり、貸し出したり、修繕して綺麗にするなどの契約行為ができなくなります。契約は本人の意思で行う必要があるため、認知症を発症すると手続きを進めることができず「フリーズ」状態になってしまいます。さらに、遺産分割協議は、本人が亡くならない限り成立しません。そのため、親御さんが元気なうちに、財産をどのように分配するのか話し合っておくことが重要です。その一環として、遺言書を作成しておくことも考えたほうがよいでしょう。
また、「任意後見」という制度があります。これは、親が生前に「自分が亡くなった後に、または認知症になった場合に、財産の管理や処分を誰かに委ねる」という契約を結んでおくものです。
最近では残念ながら、法律家による不正の問題も報道されています。例えば、広島の弁護士が預かった財産を私的に流用していた事件です。このようなリスクもあるため、他人に任せるのが不安な方には「家族信託」という制度もあります。これは、「私がもし認知症になったら、私の財産を使って適切な施設に入れてほしい」「この家も、適切なタイミングで売却してほしい」といった内容を家族に託す仕組みです。こうした事前の準備がないと、本人が亡くなるか判断能力を失うまでは何も手をつけられなくなり、結果として空き家が放置されてしまうことになります。私の母も年を重ねているので、「そろそろ準備をしておかないといけないよ」と話しています。私自身も、この問題に関しては急がなければならないと考えています。
もし空き家になった場合、その空き家の「出口」として考えられる選択肢は、大きく3つです。1つ目は、管理してそのまま維持すること。2つ目は、空き家を有効活用すること。3つ目は、空き家を手放すことです。
まず、「管理する」場合は、施錠がきちんとかかっているか、窓が割れていないかなど、安全面の確認が必要になります。また、家を長持ちさせるためには「通風・換気」も重要です。定期的に窓を開けて空気を入れ替えないと、あっという間に家が傷んでしまいます。さらに「通水」も忘れがちですが、とても大切です。通常、排水口には水が溜まっており、下水からの悪臭を防いでいます。しかし、空き家のまま放置するとこの水が蒸発し、下水の臭いが家に充満してしまうことがあります。そのため、定期的に水を流しておくことが必要です。
その他、室内の簡単な清掃や庭の手入れも欠かせません。食べ物などが残っていたら、ネズミや野良猫が住みついてしまうこともあります。また、不法投棄の被害に遭うこともあります。さらに、草刈りや剪定を怠ると庭木が大きくなりすぎて、隣家や道路に越境する可能性があります。こうなると、ご近所に迷惑をかけることになり、トラブルの原因にもなります。
また、近隣の方々に対して、「空き家になってしまい、ご心配をおかけしています」と一言伝えておくことも大切です。長期間放置されていると、周囲の人は不安に思いますし、いざ解体や売却をしようとした際に、「今まで迷惑をかけられていたのに、協力する気になれない」と言われてしまうこともあるからです。
業者に管理を依頼する場合、「とにかく安いところに頼もう」と考える方も多いですが、価格が極端に安い業者がしっかり管理してくれるとは限りません。もちろん、ボランティアのような形でやってくれる方がいればいいですが、現実的にはなかなか難しいでしょう。ですから、「管理する」という選択をする場合は、どの程度のコストをかけるのか、どのような業者に依頼するのかも含めて、慎重に考える必要があります。
空き家の管理には、多くの手間とコストがかかるため、早い段階でしっかり計画を立てておくことが大切です。
有効活用を考える場合、出口は大きく2つに分かれます。それは「家族でそのまま使う」か「貸す」かです。家族で使う場合はシンプルですが、「貸す」のはいくつかのハードルがあります。
まず、今の状態がどうなっているのかをしっかり調査しなければなりません。現状のままでは借り手がつかない場合、一定のリフォームを行う必要があるかもしれません。また、借り手を見つけるためには、仲介業者と契約を結び、広告を出して募集し、契約を進める流れになります。つまり、貸すためには、物件の状態確認、修繕、賃貸仲介契約、募集活動、入居手続きといったいくつもの手順が必要で、時間と手間がかかります。
次に「手放す」場合の選択肢についてですが、これには「売る」「解体する」「譲る」の3つがあります。
まず「売る」場合ですが、物件の状態を調査し、査定を依頼し、適正な価格を見極める必要があります。その後、仲介業者と契約を結び、広告を出して買い手を募ります。商談を進め、条件交渉を行い、最終的に売買契約を締結し、登記の手続きを経てようやく売却完了となります。
次に「解体する」場合ですが、まず解体業者に見積もりを依頼し、費用を確認する必要があります。特に、解体前に問題になりやすいのが「残置物」の処理です。これを片付けない限り解体工事は進められません。家財道具の整理・処分を終えた後に、ようやく解体工事が始まり、建物を撤去し、最終的に滅失登記を行うことになります。更地になった土地をそのまま利用するのか、それとも売却するのかは、その後の選択肢になります。
最後に「譲る」場合ですが、これは「家族や孫に引き継がせる」方法です。しかし、不動産を譲り受ける側には「贈与税」や「不動産取得税」がかかるため、予想外の税負担が発生する可能性があります。そのため、事前にしっかりと税金について確認しておくことが重要です。
また、最近では「相続土地国庫帰属制度」という仕組みが導入されており、相続人が不要な土地を国に引き取ってもらうことも可能になりました。ただし、この制度も簡単に利用できるものではないため、要件をよく確認した上で検討する必要があります。
このように、空き家の出口戦略を考える際には、それなりの手間や費用がかかります。後回しにせず、早めに計画を立て、準備を進めておくことが重要です。
そして、空き家の活用や処分には、大きく分けて3つの選択肢がありますが、どの方法でも手間や時間、お金がかかることは間違いありません。そのため、できるだけ親が亡くなったり、認知症になる前に話し合っておくことが非常に大切です。もし親御さんが「なぜ売るんだ? なぜ解体するんだ?」と反対してしまうと、持ち主が親である以上、なかなか動きづらくなります。
そうした問題に対処するために、私は 3つの整理 が必要だと考えています。
1つ目は 「お金の整理」 です。まず、その家を売った場合にいくらになるのか、解体するとどれくらいの費用がかかるのかを把握しておく必要があります。
2つ目は 「行く末の整理」 です。活用するのか、処分するのか、それぞれのメリット・デメリットを整理し、選択肢を明確にしておくことが大切です。家族や相続人の間で方針を固め、できれば親御さん自身の意向も確認しておくのが理想です。親が「こうしたい」と意思表示をしてくれていれば、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。
3つ目は 「気持ちの整理」 です。生まれ育った家は、家族にとって思い出の詰まった大切な場所です。そのため、いざ解体や売却となると、気持ちの面で割り切れないことも多いでしょう。家財道具にしても同じで、私自身も仏壇の扱いについて悩んだことがあります。すべてを残しておくわけにもいかず、どこかで区切りをつけなければなりません。
早めに動くことが重要 なのは、時間が経てば経つほど問題が複雑化し、経済的な負担も増えていくからです。放置すればするほど、建物は劣化し、処分費用がかさんでしまいます。また、相続人同士の意見がまとまらず、関係がこじれることもあります。
そうなる前に、「今後どうするか」を決めるための話し合いを、勇気を持って進めていくことが大切です。大事なのは、お互いの権利を認め合いながら、損得勘定だけでなく 「時間軸」 を意識することです。先延ばしにするのではなく、早期の決着を目指し、歩み寄る姿勢を持つことで、スムーズに前へ進むことができます。
空き家の問題は、多くの家庭にとって避けては通れない課題です。今回の話が少しでも参考になれば、ぜひ早めに家族で話し合い、準備を進めていただければと思います。ぜひ参考にしてください。