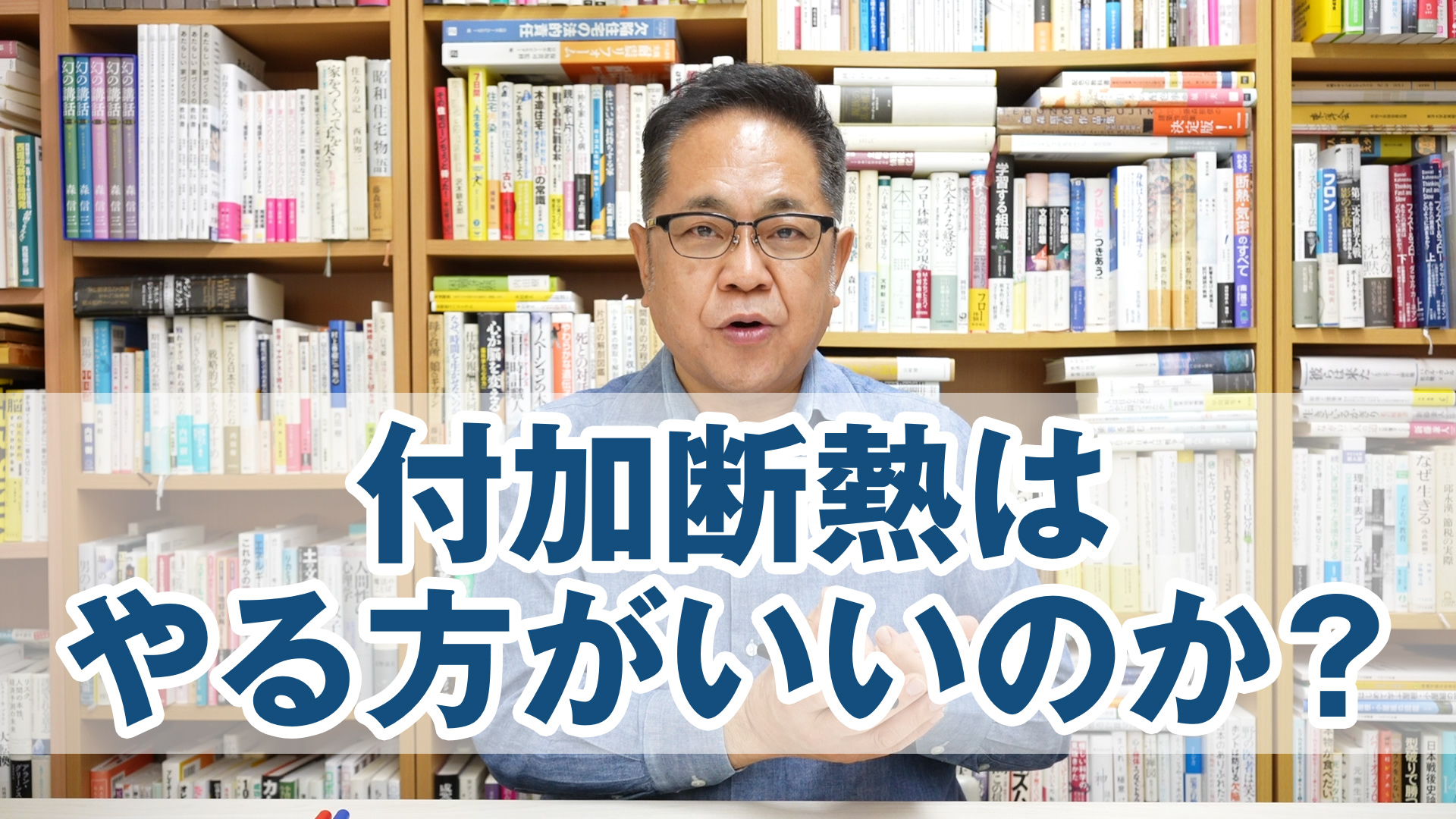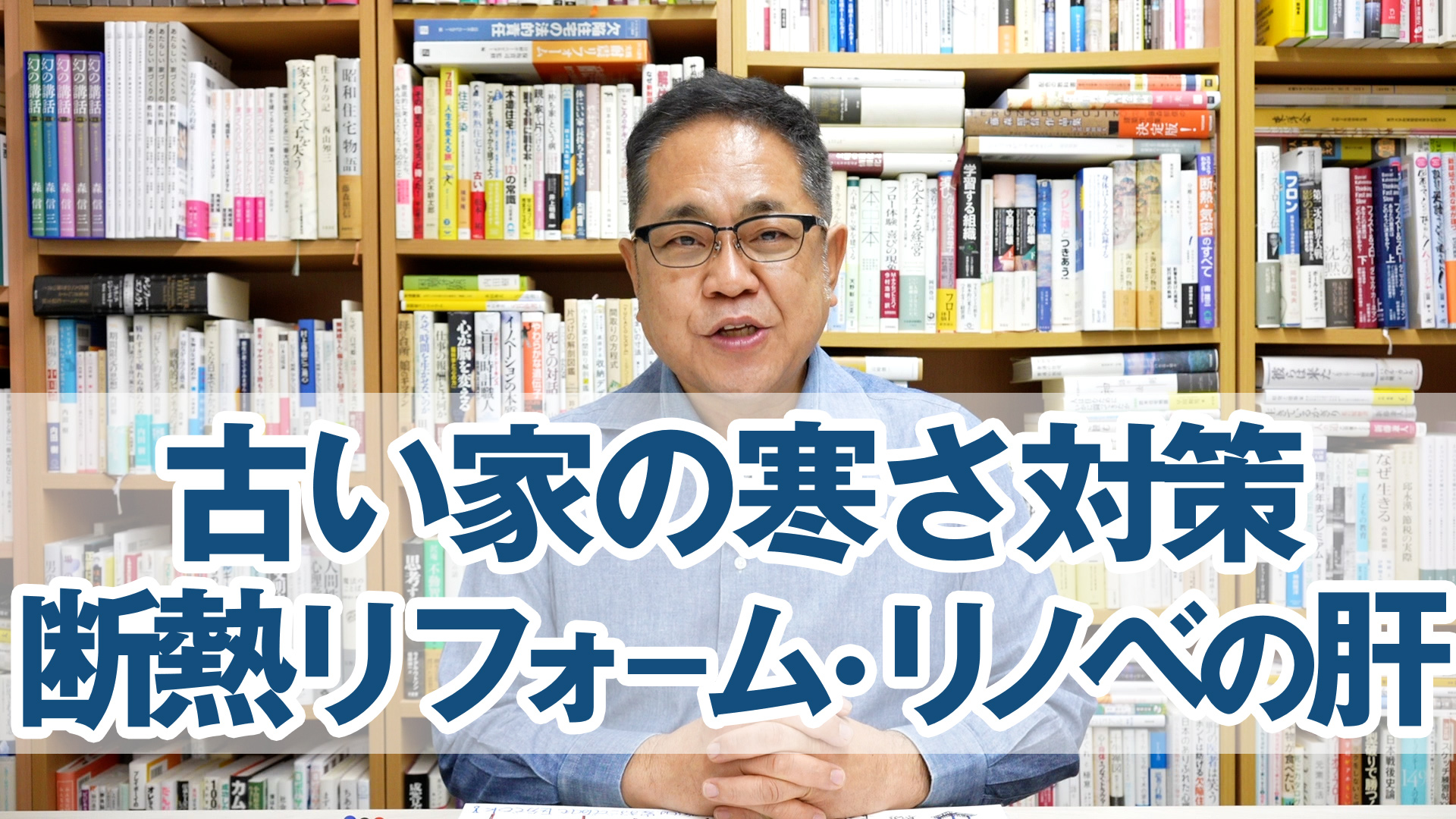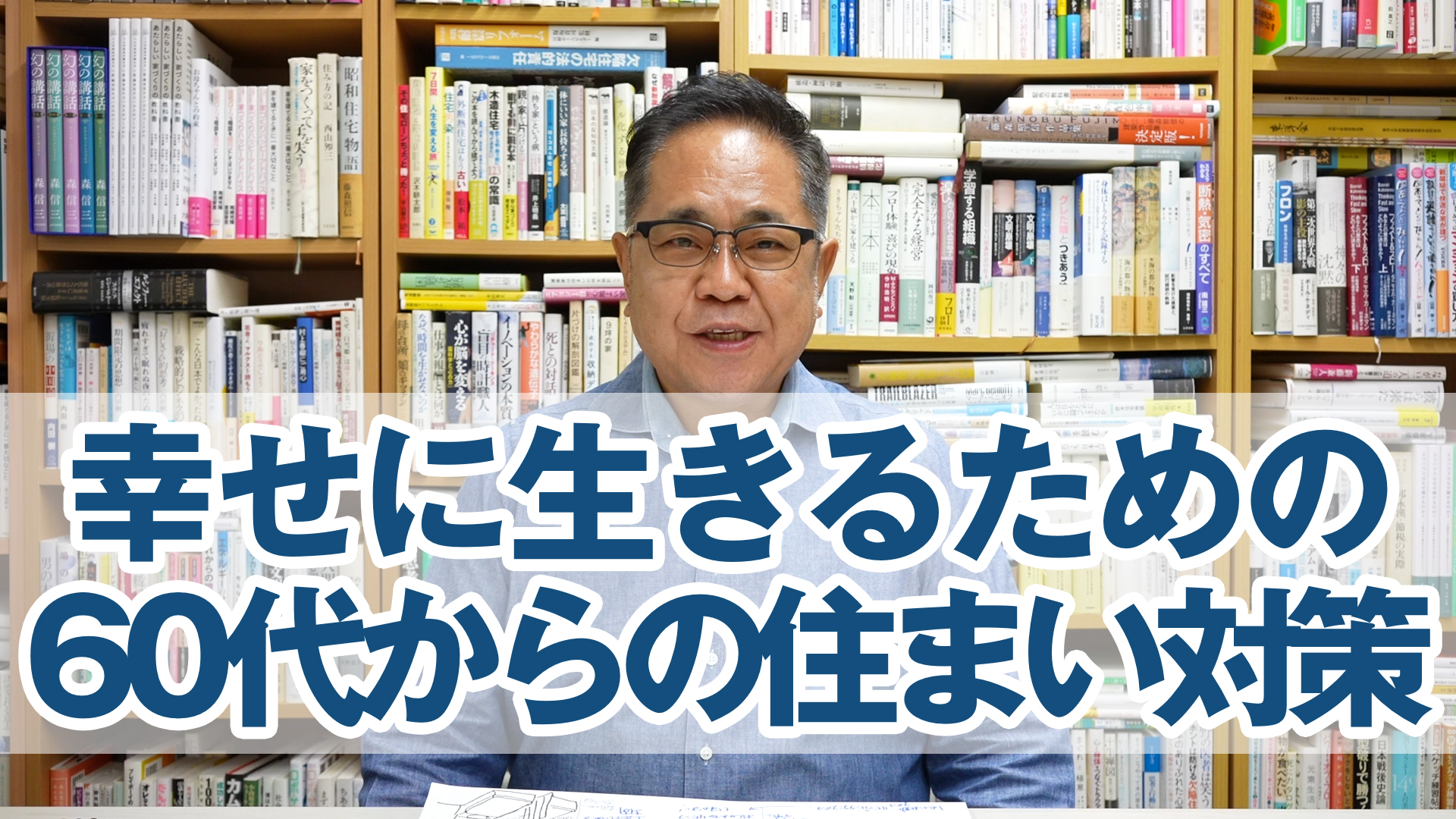間取りの新常識:テレビの居場所を自由にする
今回は、家づくりの間取りやプランを考えていく中で、行き詰まりを感じたり、新しい切り口が欲しくなったときに、少しヒントにしてもらえる話をしたいと思います。
このテーマについて話すきっかけになったのが、僕が以前から持っていた『間取りのすごい新常識』という本です。2020年に発行された少し前の本ですが、プラン作りに行き詰まったときに改めて読んでみたら、当時はスルーしていたことが、今になってズキュンと心に刺さったんです。今日はその「ズキュン」ときた話をお伝えします。
本の中で印象に残ったのが、「テレビの居場所問題」でした。みなさんも、テレビの配置って結構考えませんか?でも、この本では「テレビの居場所を自由にしよう」と提案されているんです。僕の言い方で言うと「テレビの存在を固定しない」という発想です。
たとえば、一般的な16畳程度のLDKでは、対面キッチン、4人掛けのダイニングテーブル、カウチソファー、テレビというレイアウトが多いですよね。こういう間取りだと、どうしても家族の団らんの中心がテレビになってしまう。昭和のおじさん的にはしっくりくる構図です。昔はテレビが家の中心でしたし、「お茶の間の皆さん」と呼びかけられるくらい、暮らしの中心にありました。
でも今はどうでしょうか。うちでも、今は娘が独立して出ていき、女房とおふくろと僕の3人暮らしですが、3人で並んでリビングでテレビを見ることは、もう100%ありません。団らんはあるけれど、それは食事の時間です。大画面のテレビは昔の名残でリビングに置いてありますが、実際に見るのは食堂のテーブルに置いてある小さなテレビで、ニュースや時事ネタをチェックするくらいです。
ある若い女性から「テレビってうるさいですよね」と言われたことがありました。最初は音がうるさいのかと思ったら、そうではなく「視界に入ってうるさい」という意味でした。黒くて大きくて、色気がなくて目障りだと。必要なときしか見ない、というスタンスです。
この本に載っていたプランでは、テレビがリビングの視界にほとんど入ってこないんです。玄関から土間を抜けてリビングに入ると、アイランドキッチンや丸いダイニングテーブルが見え、空間としてはとても素敵なのに、テレビの存在感がほとんどない。テレビが視界に入るのは、ソファーの特定の位置からだけ。つまり「目的を持って見ない限り、テレビは見ない」という設計なんです。
この考えに触れて、僕もはっと気づきました。うちでもソファーをテレビの方向じゃなくて、庭の方に向けた方が心地いいんじゃないかと。テレビのためにリビングの配置を決める必要はないのかもしれません。
もう一つ、驚いたのが「可動式テレビボード」のアイデアです。玄関土間と一体化した大空間の中で、テレビボードがグイーンと出てくるんです。普段は見えないところに収納されていて、必要なときだけ現れる。これなら、たとえばチャリンコを磨きながらレースを見ることもできるし、仲間と大谷選手の試合を見る時なんかにも活用できる。これは家づくりの新しい可能性だと感じました。
この発想を見て思ったのが、「テレビはもっと自由でいい」ということ。僕らが仕事で使っているモニタースタンドのように、家の中でもゴロゴロ動かせたらいい。実際、セミナーでもそういう使い方をしているわけで、なぜ家だけが固定化されているのか不思議に思いました。
僕は「我が家でスポーツカフェをやる」というのが、ひそかな夢です。大きなテーブルを囲んで、家族や友人たちとスポーツ観戦をする。普段は夫婦2人で静かに過ごしていても、孫や子どもたちが集まったときには、じいじがケーキやお酒を振る舞いながら、みんなで盛り上がる。そんな非日常のひとときを実現するための間取りって、あってもいいんじゃないかと思うんです。
もちろん、しょっちゅうやるわけではありません。年に数回、イベントのような感覚です。でもそのためにテレビを固定する必要はない。普段は目につかない場所にしまっておいて、イベントの時だけ引っ張り出せばいいんです。
団らんは大切です。でも、団らんの場をテレビに縛られる必要はない。むしろ自由にしてしまった方が、より豊かな時間を過ごせるような気がします。たとえば、年末に家族が集まって紅白歌合戦を一緒に見る。それはそれで楽しい。でも、普段はテレビのない空間で、それぞれが心地よい時間を過ごすという選択肢があってもいいと思います。
こんなふうに、「テレビの居場所を自由にする」ことで、間取りの新しい切り口が見えてくるかもしれません。この本に書かれていたのはその一例ですが、読者それぞれが自分の価値観に触発される部分があると思います。ぜひ参考にしてみてください。
僕もプランを考えるときに行き詰まることがありますが、「この家族にとって本当に欲しいものは何だろう」と問い直すと、意外なアイデアが広がってきます。そんな時に、今回のような本や考え方がヒントになると嬉しいです。