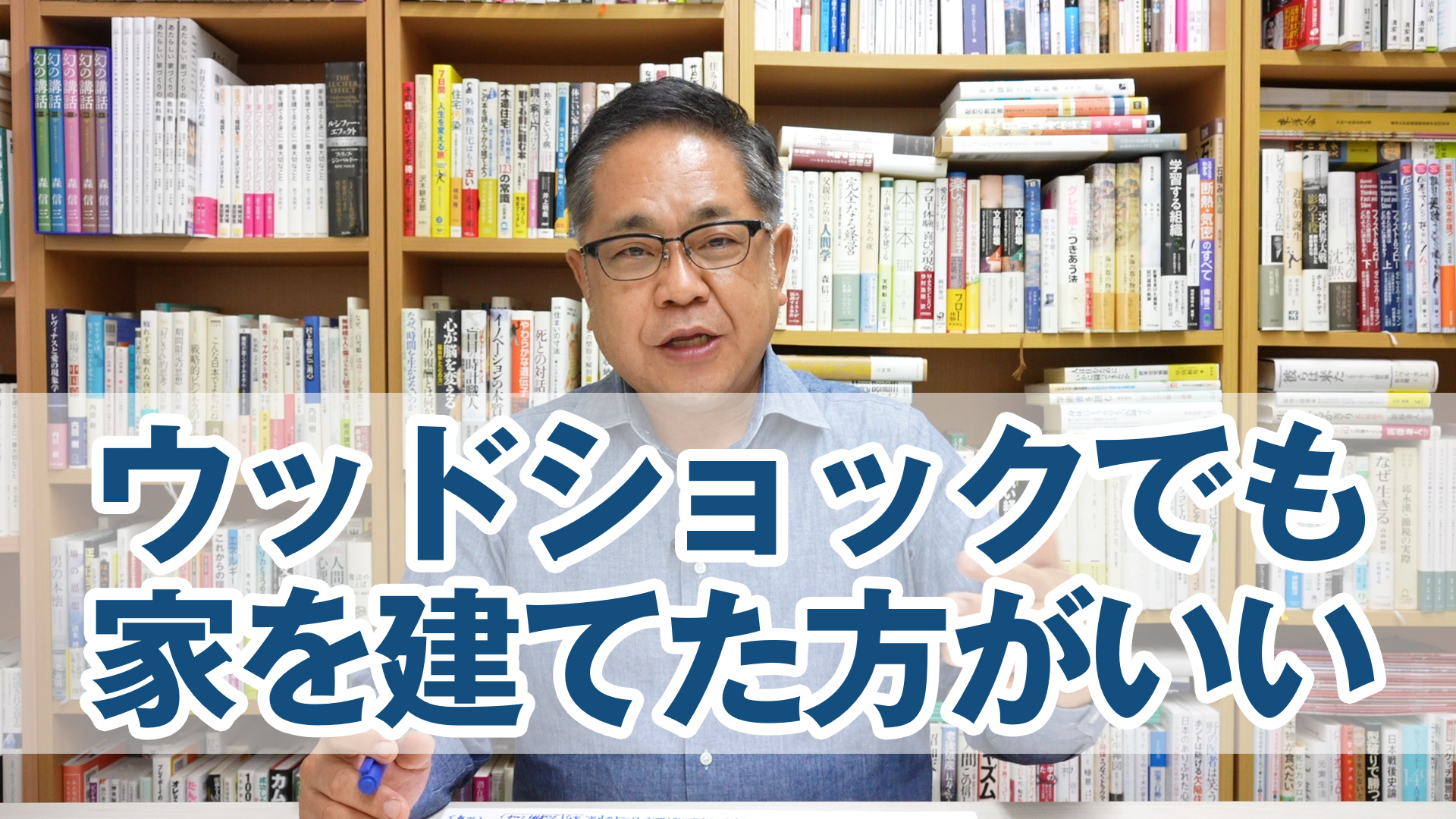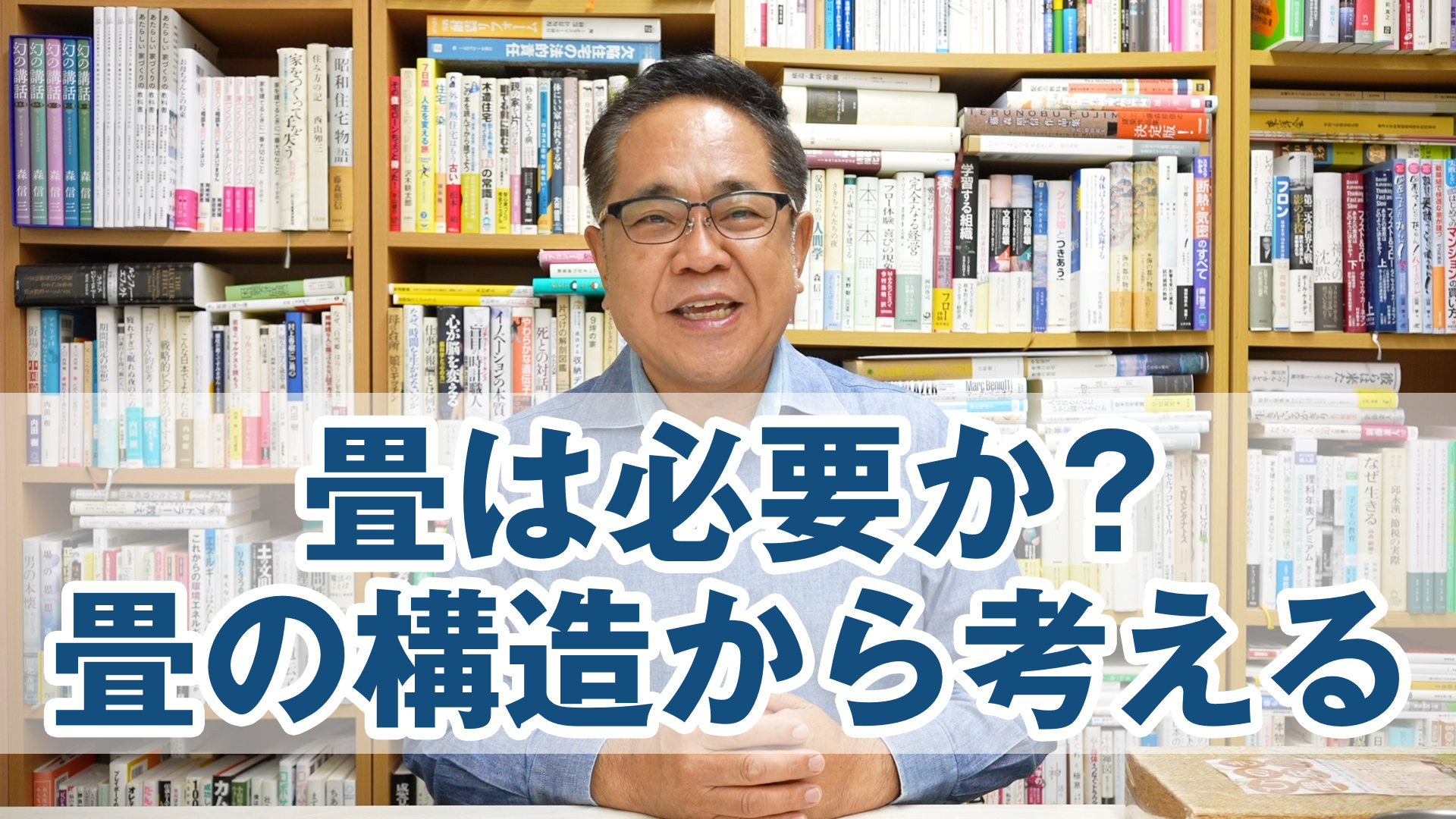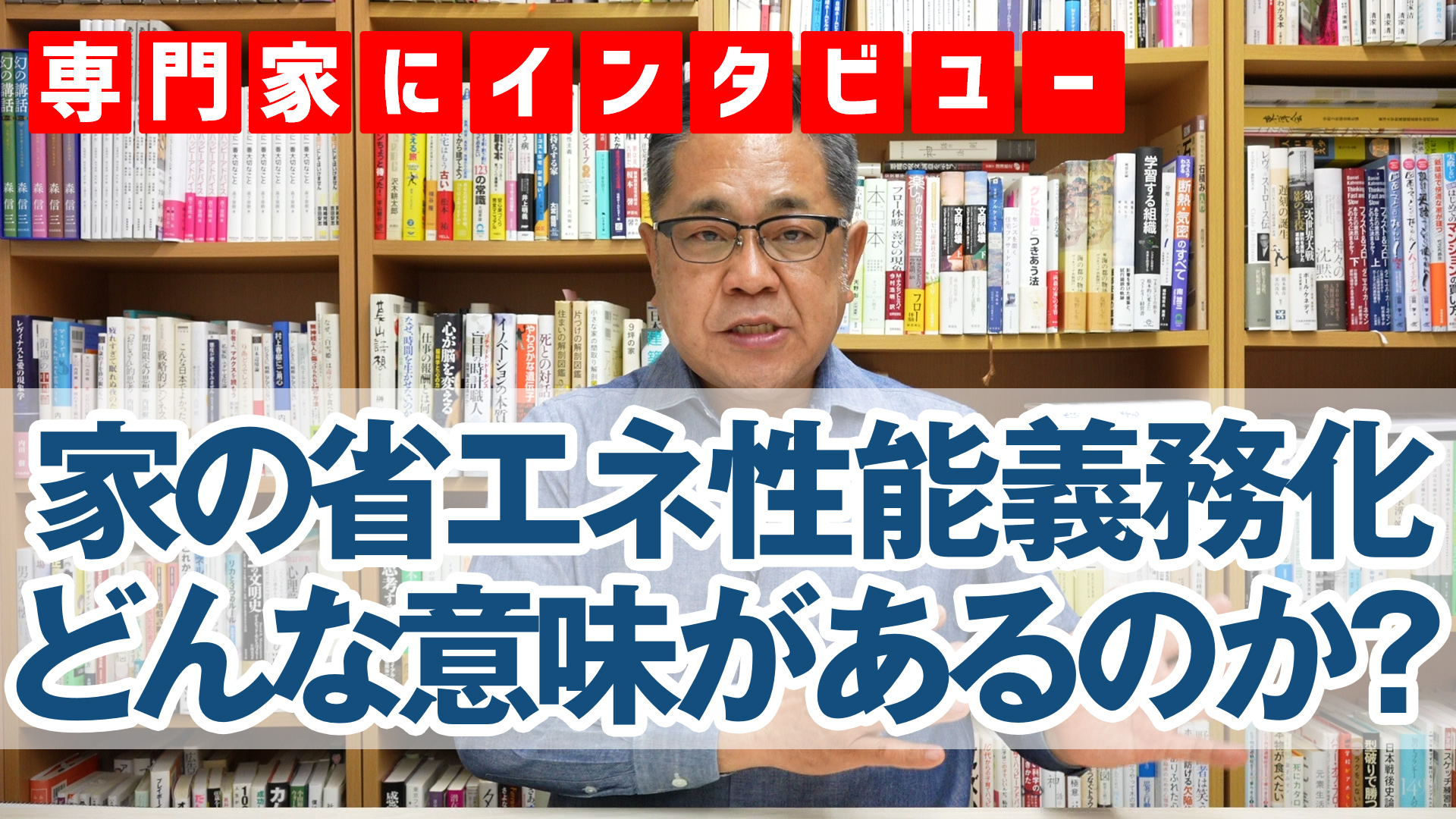間取りのセオリー12
今回は「間取りのセオリー12」について解説します。
家づくりを真剣に考え始めると、多くの方が気にされることの一つに、「良い間取りを作りたい」という思いがあると思います。間取りについていろいろと考える際に、非常に参考になる本を見つけました。その本はエクスナレッジ社から出版されている、松原正明先生が書かれた『間取りスケッチブック』という本です。さまざまな間取りの実例が豊富に掲載されており、詳しい解説もついていて、とても素晴らしい内容になっています。ただ、この本には「効果的な読み方がある」と感じました。そこで、この本の魅力を紹介しながら、より効果的に活用するためのポイントを解説したいと思います。
多くの方は「ああ、こんな間取りがあるのか」と流し読みをされるかもしれませんが、その読み方では、この本の価値を十分に引き出せないのではないかと感じています。本には「読み方」がありますよね。この本にも意識してほしい読み方があります。それが「間取りのセオリー12」です。この部分をしっかりと読んでから本編に進むことで、より深く内容を理解し、間取りの考え方を学ぶことができると思います。まずはこの部分の解説を聞いた上で本を読んでいただくと、より多くの気付きが得られると思います。
セオリー1は、間取りを考える際に「どこにリビングを配置するのが最適か」が大切です。「最適な場所」とは何かを考えると、まずは日当たりです。もう一つは眺望です。例えば、西側に素晴らしい景色が広がっている場合、日当たりだけでなく、景色の良さも考慮してリビングの位置を決めるのが良いでしょう。加えて、周囲の環境も考慮する必要があります。隣家との距離、公園の有無、隣接する建物の種類などが影響します。「日当たり・眺望・環境」の3つのバランスを見極めながら、最適なリビングの位置を決めるのが大切です。
セオリー2は「玄関から奥へ行くほどプライベートな空間になるように考える」ことです。例えば、玄関から入るとまずLDKがあり、ここは家の中では比較的パブリックな空間になります。一方、寝室やクローゼットなどはプライベート空間に分類されます。このように、家の奥へ進むにつれて、パブリックからプライベートへと変化していくように設計するのが理想的です。
セオリー3は、玄関の配置についてです。多くの場合、玄関は道路に近い位置に設けることが一般的ですが、その際に注意すべき点が、家の中が外から丸見えにならないようにすることです。設計上、玄関が真正面から見えてしまう場合は、グリーンや格子を使って目隠しをするのが良いでしょう。また、玄関のドアを道路に対して直線的に設けるのではなく、少しクランクさせる(角度をつける)ことで、視線を遮る工夫をすることも有効です。
セオリー4は、階段の配置についての考え方です。実は、間取りを作る際に階段の配置を後回しにしてしまうケースが多く、設計初心者がよく陥るミスの一つでもあります。私も経験がありますが、新人のスタッフが間取りを作った際に、「良い間取りができました!」と見せてくれたものの、「ところで階段はどこ?」と尋ねると、「あっ、忘れていました…」ということが実際にありました。大学生時代にも、こうした失敗談はよく耳にしました。そこで、間取りの基本を押さえた後、次に考えるべきなのは「階段をどこに配置するか」です。階段は住宅の面積や使い勝手を大きく左右するため、慎重に考える必要があります。松原先生は「階段はなるべく家の中心に配置するべき」と述べています。特に、2階建ての場合、階段の上り口が2階の中央にあると、そこを基点にクローバー型に各部屋を配置できるため、廊下を最小限に抑えられます。廊下が少なくなれば、その分、居室に使える面積が増え、コンパクトで経済的な家づくりが可能になります。
セオリー5は、水廻りの配置についてです。水廻りは、LDKと個室群(寝室や子ども部屋など)の間に配置するのが基本です。最初に「セオリー1」でリビングの位置を決めると、必然的にLDKの場所が決まります。次にゾーニングを考え、2階への階段の位置を決めた後、個室群の配置が決まるのですが、その間に水廻りを配置しないと、家事動線が不便になってしまいます。そして意外とよくあるのが「洗濯動線が長くなってしまう」ケースです。例えば、洗濯機がある場所と干す場所が遠かったり、脱衣所からクローゼットへの動線が悪かったりすると、日々の家事が不便になってしまいます。そうならないよう、水廻りの配置は注意する必要があります。
セオリー6は、できるだけ朝日が入る方角にダイニング・キッチンを配置するのが理想的とされています。朝日が入るダイニング・キッチンは、朝の時間を気持ちよく過ごせる空間になります。朝日を浴びながら朝食をとることで、一日のスタートをより快適なものにすることができます。
セオリー7は、外構や植栽の計画についてです。間取りの設計に夢中になると、どうしても外構計画が後回しになりがちです。その中でも特に見落とされやすいのが「植栽」です。間取りのゾーニングを決める際、庭の配置や隣家の位置、道路との関係も把握できるはずです。その時点で、どこに木を植えるかを考えておくことで、住まいの印象が大きく変わります。たとえデザイン性の高い家を建てたとしても、植栽が一切ないと、どこか無機質で冷たい印象になってしまいます。逆に、木を1本植えるだけで、家に「生命感」が生まれ、ぐっと雰囲気がよくなります。
セオリー8は、玄関とリビングの関係についてです。最近の間取りでは、玄関ホールからすぐリビングにつながる設計が増えています。これは、無駄なスペースを省き、効率的な動線をつくる上では合理的ですが、一方で「道路からの視線」に配慮しなければなりません。玄関ドアを開けた瞬間に、リビングの中が丸見えになってしまうと、プライバシーの確保が難しくなります。そのため、リビングの入口を少しクランクさせる(角度をつける)ことで、視線が直接入らないように工夫するのが理想的です。ただし、工務店や設計士の中には「玄関から直接リビングに入る設計でも問題ない」という考えを持つ人もいます。その場合は、リビングの前に庭を設けることで、視線をコントロールするという方法を取ることが多いです。家全体のデザインや敷地条件を踏まえ、適切なバランスを取ることが重要です。
セオリー9は、トイレの配置についてです。リビングの隣にトイレを配置することはよくありますが、リビングに入った瞬間にすぐトイレのドアが見えるような間取りは、好まれないことが多いです。特に、家族の中でも気にしない人と、絶対に嫌だという人に分かれるケースがよくあります。この問題を解決するためには、トイレの前に「緩衝帯」を設けることが大切です。例えば、廊下を挟んだり、洗面所のホールを経由してトイレに入るような設計にすると、直接的な視線や音の問題を防ぐことができます。
セオリー10は、廊下の役割についてです。最近は「廊下のない家」を好む人が増えており、できるだけ廊下をなくしてコンパクトな間取りにする傾向があります。これは、床面積を有効に使い、コストを抑えるという目的においては理にかなっています。しかし、廊下を完全になくしてしまうと、リビングが単なる「通路」になってしまう問題が発生します。個室群の出入りがすべてリビングを経由する形になると、リビングが常に人の往来で落ち着かない空間になってしまいます。本来、リビングは家族がくつろぐ場所であるべきなのに、人が行き交うのは本末転倒です。そこで、リビングの出入り口は「2カ所程度」に絞ることが推奨されています。出入り口を制限することで、リビングがただの通路にならず、落ち着いた空間を保つことができます。
セオリー11は、リビングからの車の見え方についてです。車好きの人にとっては、リビングから愛車を眺められる設計は魅力的に感じるかもしれません。しかし、そうでない場合は、リビングから駐車スペースが丸見えになることがデメリットになることもあります。リビングから駐車場が見える場合は、植栽や壁を使って視線を遮る工夫をするのが理想的です。木やフェンスなどで程よく隠すことで、リビングの景観を守りつつ、車の利便性も確保することができます。
最後のセオリー12は、「間仕切りを少なくする」考え方です。特に昔の家では、冷暖房効率を上げるために部屋を細かく区切ることが一般的でした。しかし、現代の家は高気密・高断熱が基本になっているため、昔のように必要以上に仕切る必要はありません。例えば、夏の暑い時期にエアコンをつけてリビングだけ涼しくしても、廊下や台所、お風呂場などが暑いままだと、結局家の中で不快な場所が生まれてしまいます。家のどこにいても快適に過ごせるようにするには、できるだけ空間を広くつなげて、空調の効率を全体的に高めることが重要です。特に、春や秋などの気候が穏やかな時期には、仕切りを開放して風を通すことが多いですよね。このように、普段は仕切らずに広く使い、必要に応じてだけ仕切るという設計の方が、現代の家には適しています。また、最近は「無駄をなくす」という意識から、廊下を極端に減らしたり、ホールを小さくしたりする間取りが増えています。しかし、それによって動線が悪くなり、暮らしにくくなることもあります。単純に廊下をなくせばいいというわけではなく、快適な生活空間を作るために、どこにどの程度のスペースが必要なのかをしっかり考えることが大切です。
このセオリー12を意識しながら、さらに松原先生の本を読むと、より深く理解できると思います。ぜひ参考にしてください。