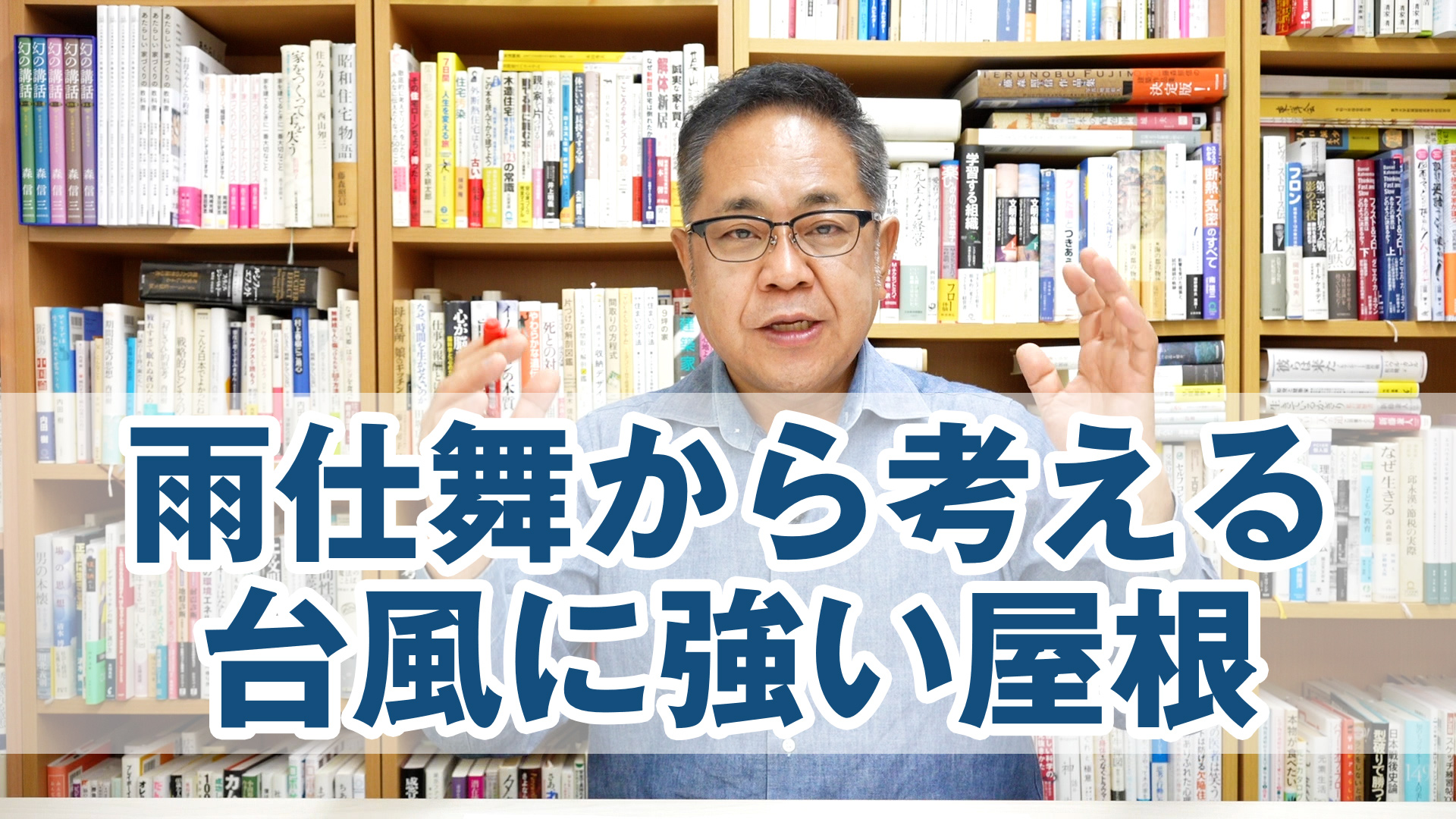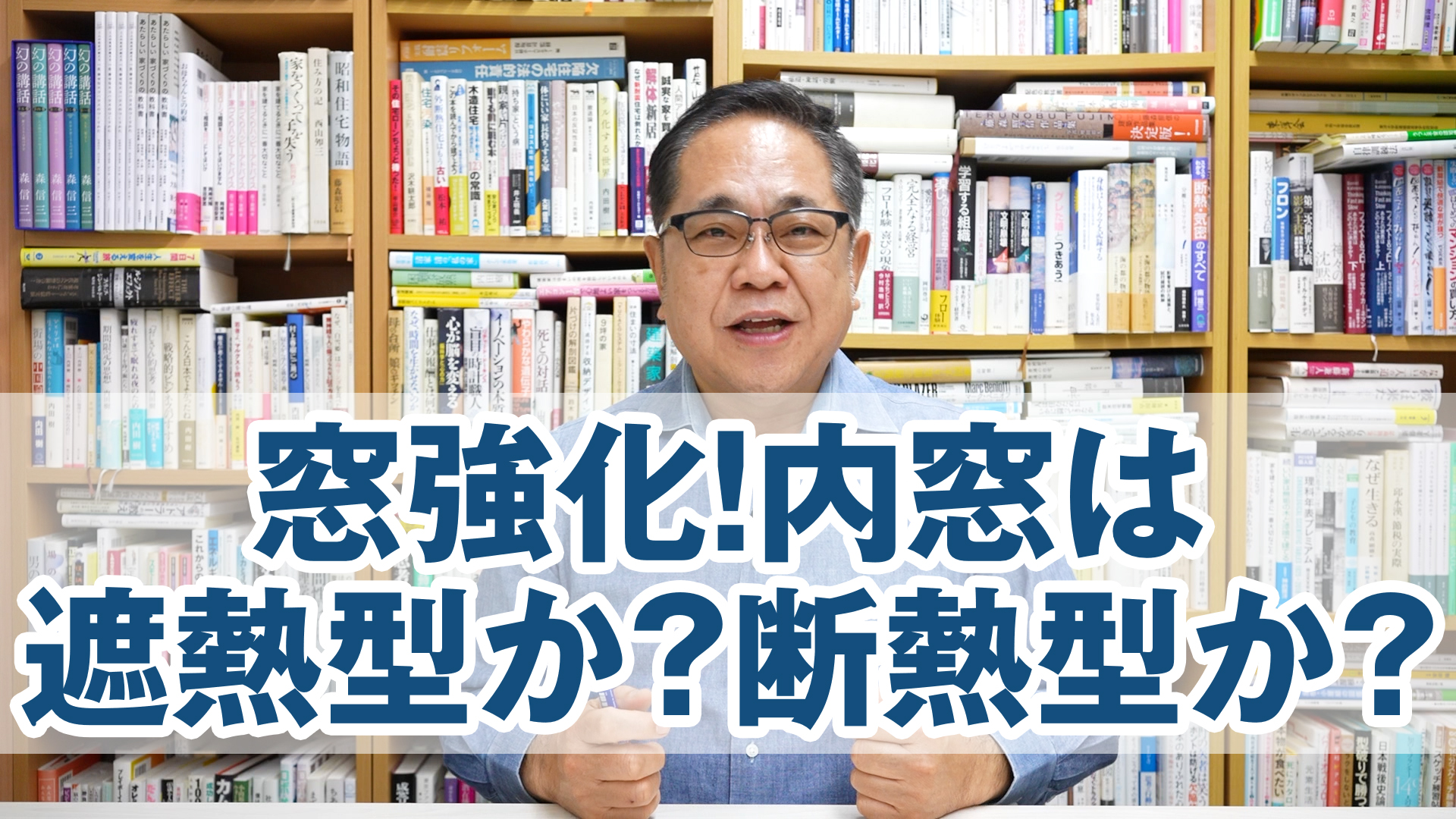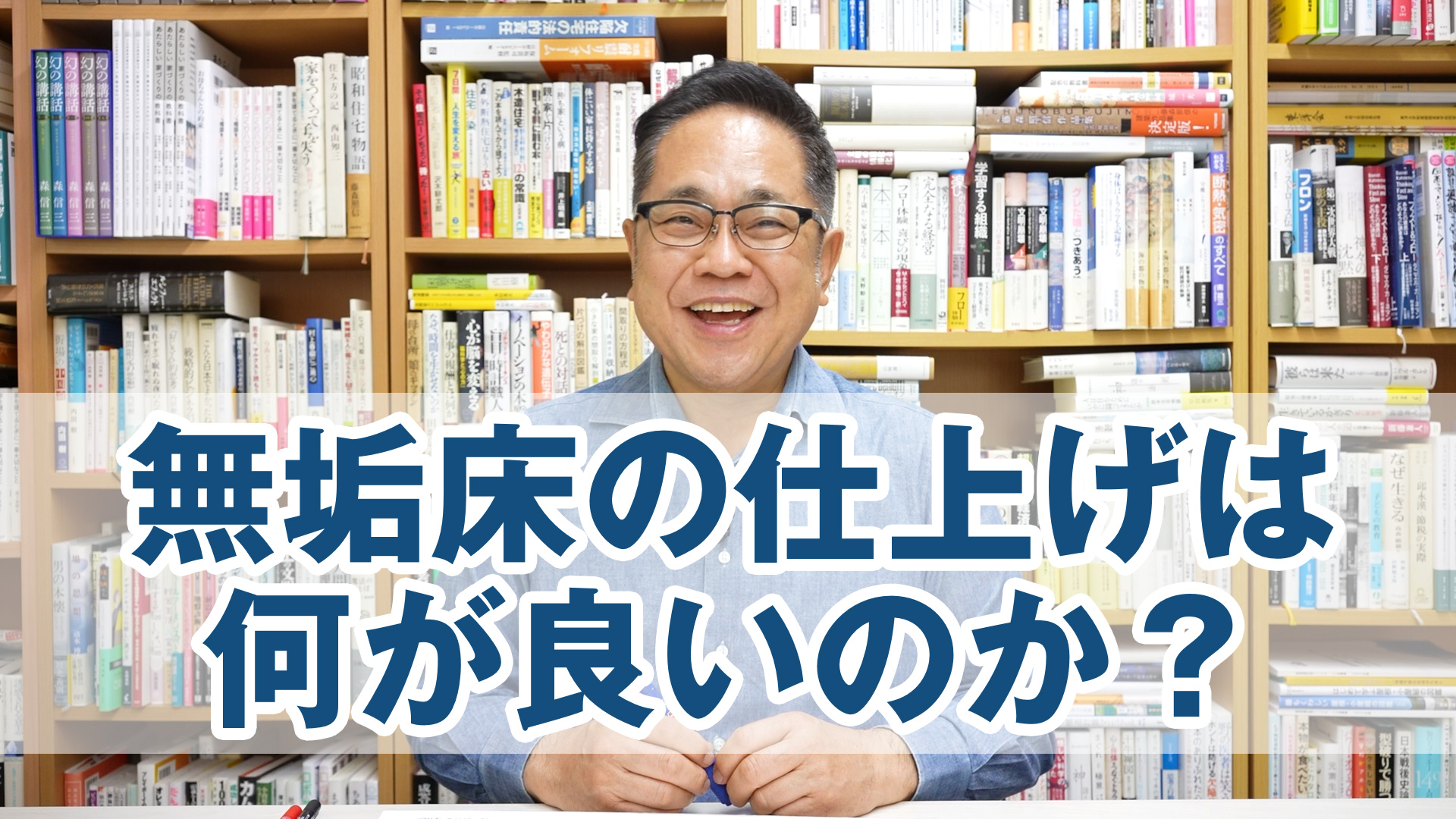基礎断熱と床断熱はどちらがいいか?
今回は「基礎断熱と床断熱はどちらがいいか?」について解説します。
寒い季節になると、周りの女性からよく「足元が冷たい」「なんとなく足元が寒くて落ち着かない」という声を聞きます。特にこの時期、家づくりを検討している打ち合わせの現場では「足元が暖かい家にしたい」といった話題がよく出てきます。その中で、よく「足元を暖かくしたいのですが、基礎断熱と床断熱どちらを選ぶべきなのか?」という質問をいただきます。そこで今日は、このテーマをもとに解説していきたいと思います。
まず、「基礎断熱」と「床断熱」という言葉の意味がわからない方もいらっしゃると思いますので、それぞれについて説明していきます。この図は、2つの断熱方法を示した家の断面図です。ご覧のとおり、建物には基礎があり、その上に1階の床があり、さらに壁や柱が立ち上がって屋根がある構造になっています。これまで一般的だったのは、床を断熱する「床断熱」という方法です。通常、床下は湿気を逃がすために外気が入る構造になっています。そのため、外気の冷気や湿気が床下に出入りしますが、その上のラインで断熱を施すのが「床断熱」という方法です。
一方、「基礎断熱」は基礎部分の立ち上がりを囲むように外壁の延長として基礎全体を断熱する方法です。ただし、基礎はコンクリートでできていますよね。コンクリートは触ると冷たく、断熱性能が低いため、冷たさや暑さがそのまま伝わってしまいます。さらに、コンクリートは熱容量が大きいため、冷たい場合はその温度を長時間保持してしまうことがあります。基礎断熱では、例えば基礎の立ち上がり部分とその内側、60cm程度の区間をL型に断熱材で覆うことで、コンクリートの冷たさが室内に伝わらないようにします。この方法は「基礎内断熱」とも呼ばれますが、外側を断熱する「基礎外断熱」という方法もあります。寒冷地では地盤の温度が大きく下がるため、基礎全体を断熱する方法が採用されることもあります。私たちの6地域など瀬戸内海式の温暖な地域で取り入れているのが「基礎内断熱」です。一方、北海道や長野県では「凍結振動」といって地盤の温度が非常に下がることがあります。そのため、地盤の下側にも断熱を施す方法が採用されることがあり、これが「基礎外断熱」です。これらを総称して基礎断熱と呼びます。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。例えば、床断熱のメリットは、同じ断熱材の厚みで施工した場合、UA値が基礎断熱よりも高くなる点です。また、床断熱はこれまでの実績が豊富なので、寒冷地のような厳しい寒さの地域に適していると考える方も多いです。それから、非常に稀なケースですが、例えば床下浸水が発生した場合、断熱材が直接濡れることがないため、断熱性能の被害が少ないという点があります。また、床下に外気が出入りする構造であるため、湿気が溜まりにくく、カビが発生しにくいという利点があります。さらに、湿気の多い環境ではシロアリが寄り付きやすいのですが、そのリスクも軽減されるとされています。加えて、施工に慣れた工務店が多いため、コストが比較的安価である点もメリットの一つです。
一方、床断熱には場所によりますが短所もあります。例えば、建物には給湯や給水設備が必要ですが、冬場に給湯器から蛇口までの間で水が冷えてしまうことがあります。この場合、最初に出てくるお湯が冷たく感じられ、ストレスになることもあるでしょう。特に、床下に外気が入る構造の場合、外気温と同じくらいに給水・給湯管が冷やされてしまうリスクがあります。極端な寒冷地では、適切な保温をしないと管内の水が凍る可能性もゼロではありません。このように、地域や状況によって短所が顕在化する場合もあります。
次に、基礎断熱のメリットについて説明します。基礎断熱では気密性を確保しやすいと言われています。床断熱も施工に慣れている職人であれば問題なく気密を取れますが、慣れていない場合、壁や柱の接合部分に隙間が生じることがあります。その結果、隙間風が入り込み、断熱効果が十分に発揮されないケースもあります。その点、基礎断熱では施工時に気密性を確保しやすい利点があります。また、冬場には給水・給湯管が基礎内を通るため、外気温の影響を受けにくく、水やお湯が冷えにくいという特徴もあります。これにより、最初から比較的温かい状態のお湯が出やすく、ストレスが軽減されます。
さらに、基礎断熱の大きなメリットとして、床下エアコンなどの空調システムを利用できる点が挙げられます。ただし、皆さんが誤解しがちなのは、断熱だけで家が暖かくなるわけではないということです。高性能な断熱を施した場合を除き、ある程度コストバランスを考えた断熱仕様では、熱源がなければ家を十分に暖かく保つことはできません。そのため、断熱性能が高い家でも熱源の設置は重要です。基礎断熱を採用すると、床下空間を暖房に活用できるため、足元の温度が快適に保たれやすくなります。足元が暖かいと体全体が快適に感じられるため、この点は大きなメリットです。また、コンクリートの蓄熱性を活用することで、日中に取得した熱を夜間に放出し、室温を安定させる効果も期待できます。
ただし、基礎断熱には注意点もあります。コンクリートは完全に乾燥するのに1年ほどかかると言われており、その間に湿気がこもるとカビが発生するリスクがあります。このリスクを軽減するためには、換気を積極的に行うことが重要です。私たちは床下エアコンを設置することで湿気を抑えていますが、状況に応じて換気ファンや扇風機を利用することも効果的です。
そして、この10年ほどで基礎断熱は寒冷地でも高い評価を受けるようになり、採用が増えています。そのため、「どちらが絶対に優れている」ということではなく、家全体の仕様や地域の条件に応じて最適な選択をすることが重要です。例えば、床下浸水のリスクが高い地域では床断熱が適している場合がありますし、床下空間を暖房に利用する設計では基礎断熱が効果的です。
最後に、床断熱を採用する場合についてお話します。一般的に、土台の大きさは105mm程度で設計されることが多く、この場合、断熱材の厚みは10〜12cm程度が限界となります。かつては50mmや60mm、さらには30mm程度の断熱材で施工されていた時期もありましたが、現在では最低でも100mm(10cm)の厚みが必要です。この厚みがなければ、足元の暖かさを十分に感じることは難しいと考えられます。また、広島の建築界の巨匠である絹川先輩から教えていただいたのですが、床断熱を15cm程度にすると、ほとんどのケースで不満が解消されるとのことです。ただし、15cmの断熱材を使用する場合、断熱材の容積が増えるため、樹脂系の素材ではコストが高くなりがちです。そのため、グラスウールのような繊維系の断熱材を使用するケースが多いのですが、この場合は風を通さないシートを併用することが重要です。繊維系の断熱材は風を通しやすい性質があるため、シートを絡めて施工することで15cmの断熱層を作り、非常に暖かい環境を実現できます。
実際に私もこの方法を試してみたところ、確かに効果がありました。この仕様であれば、床下エアコンを使わなくても十分暖かさを感じられる場合があります。そのため、新築の場合には床下エアコンを勧めることが多いのですが、リノベーションの場合には断熱材の強化が満足度を高めるポイントになると実感しています。
このような点を踏まえ、現在進めている計画が新築かリノベーションかを考慮しながら、断熱材の種類や厚み、空調システムとの組み合わせなど、家全体の設計バランスを考慮することが大切です。ぜひ参考にしてください。