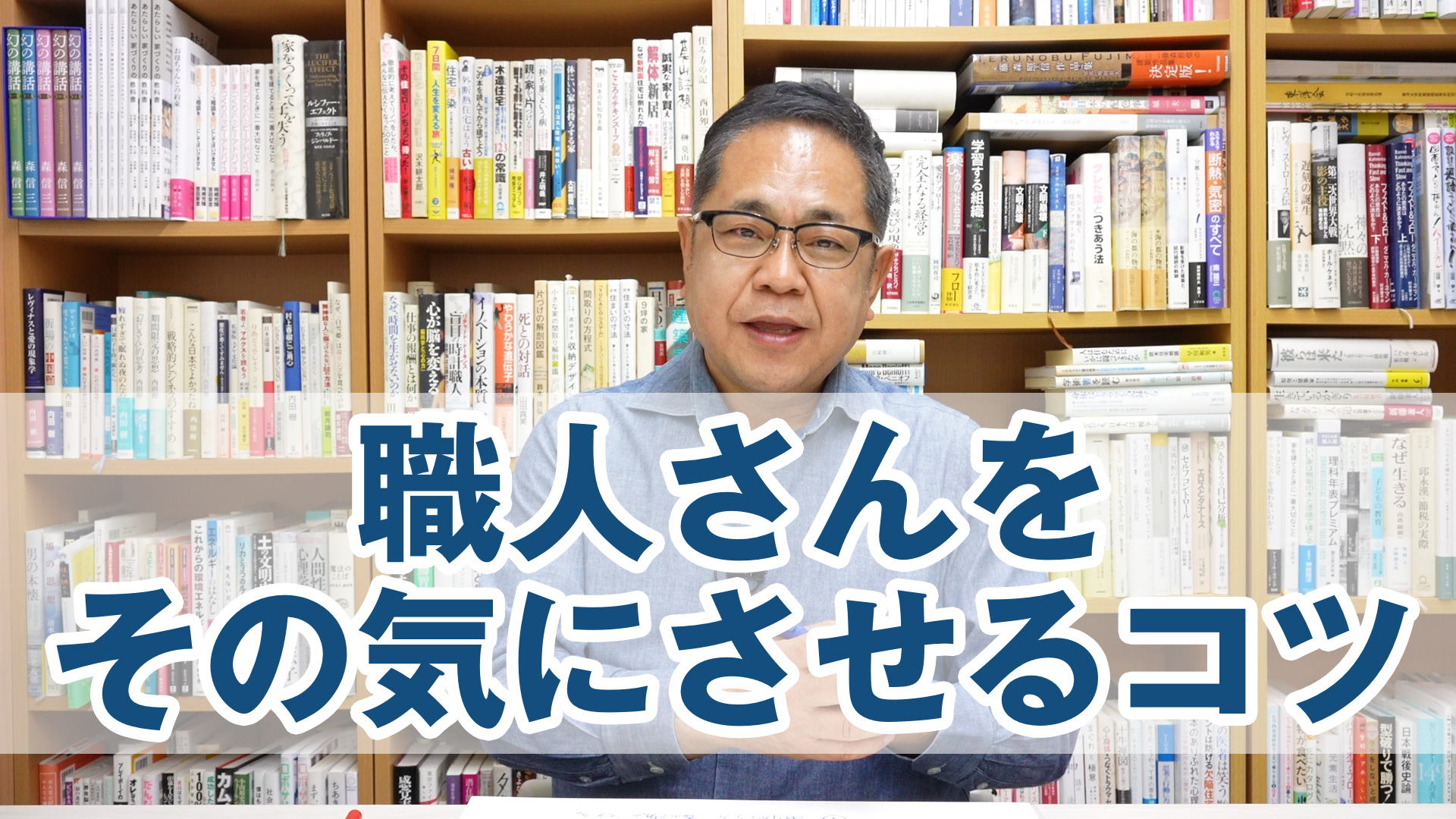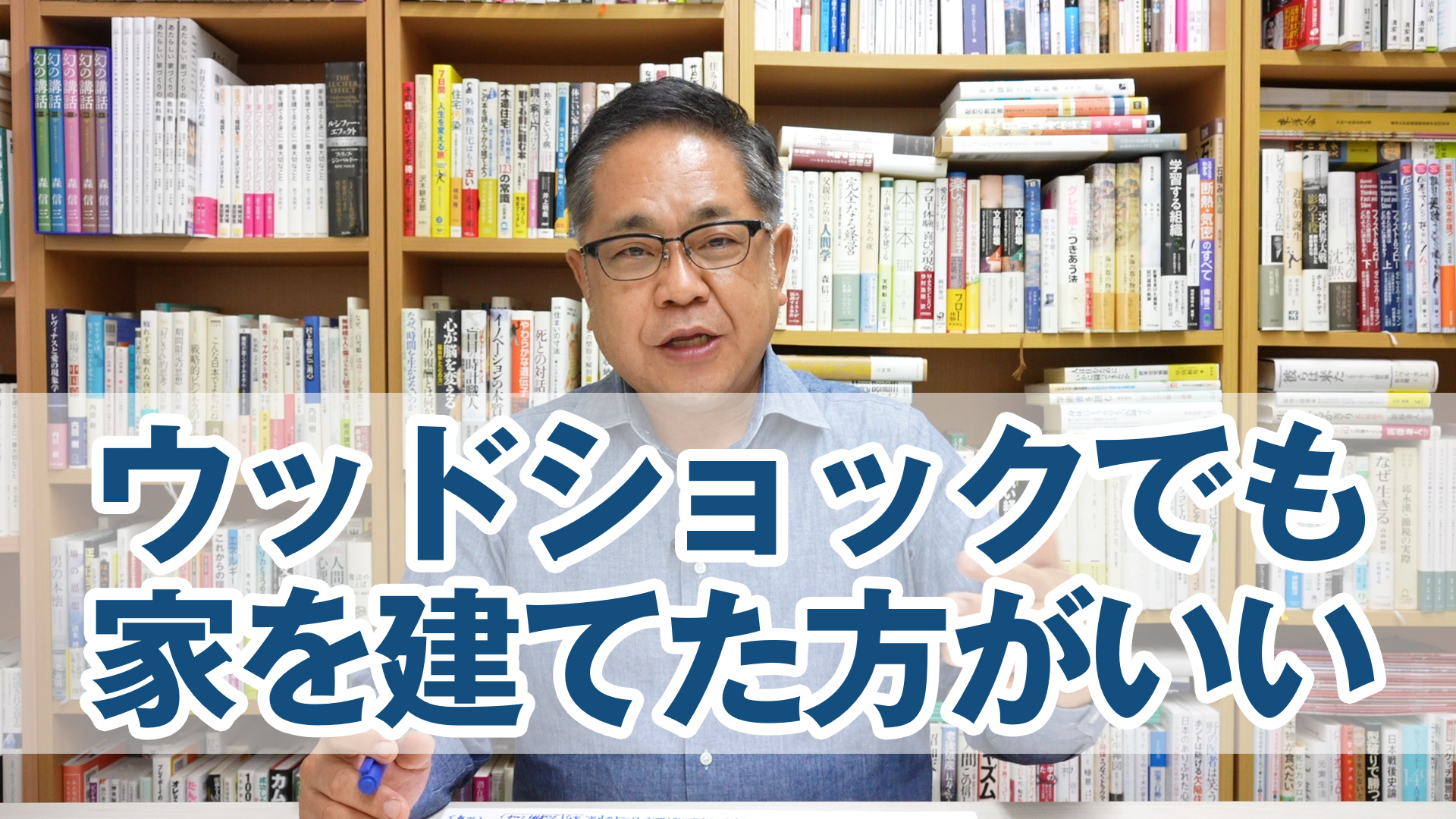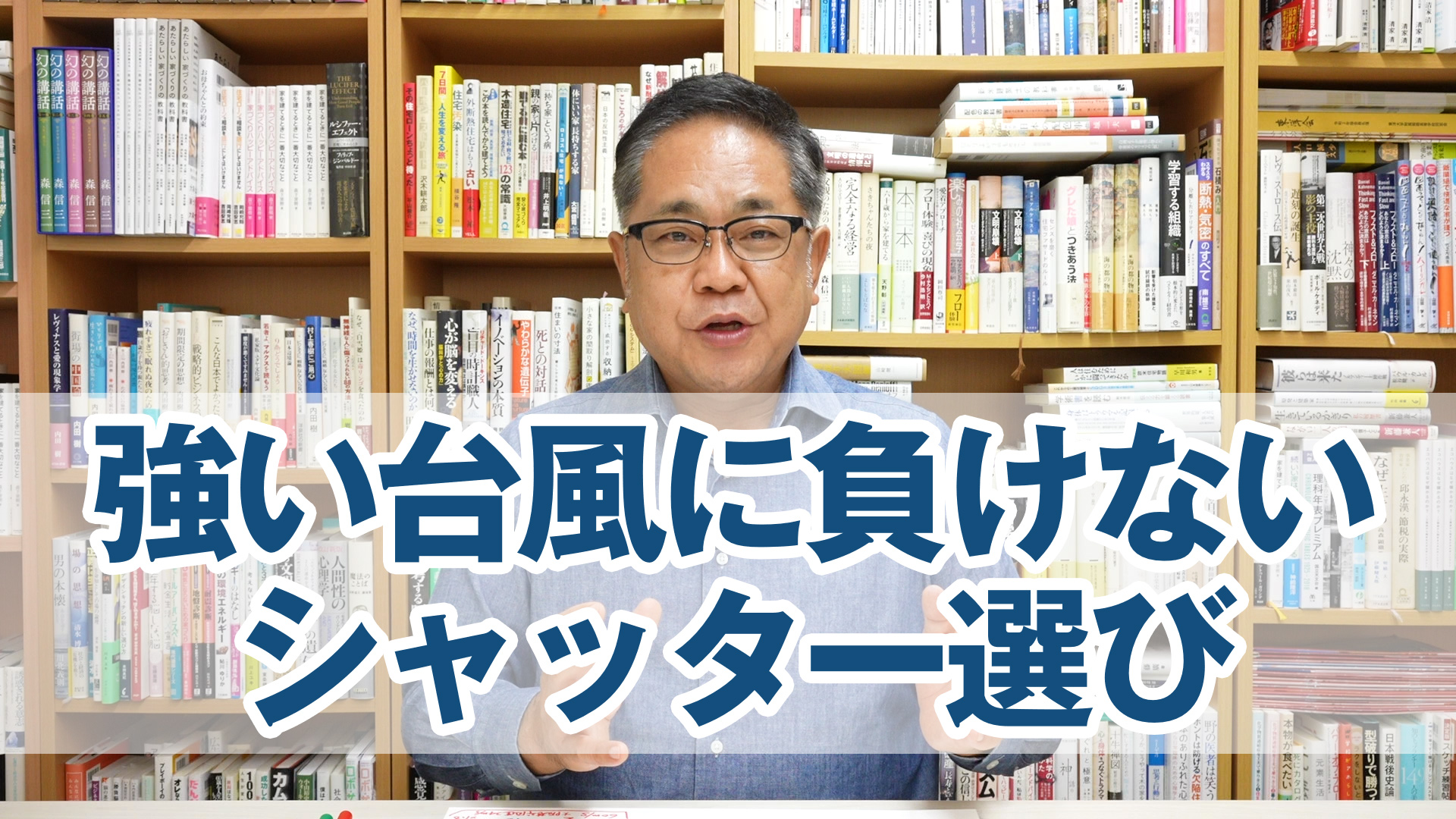気密測定をした方が良いのはなぜか?
先日「気密測定ってやった方がいいんですか?」という素朴な質問をいただきました。当たり前すぎる話かもしれませんけど、大事なことなので、もう一度改めて解説をさせていただきます。
まず「気密測定ってどういうものなの?どういう原理なの?」というところが、実際よくわからないと思うんです。「何を調べている測定なのか」という点について解説します。
これはあくまで説明用の極端なモデルですけど、家には「気密が悪い家」と「気密がいい家」の2種類があると言っても過言ではありません。中間のような家もあるかもしれませんが、実際にははっきり分かれる傾向があります。
気密が悪い家はどうなるかというと、測定用の送風機をガッと回して空気を外に出したとき、隙間が多いので外からどんどん空気が入ってくるんです。つまり、圧力の差が出にくい。でも空気はいっぱい送風されるので、送風量は大きくなります。逆に気密が良い家は、隙間が少ないので空気が外に出るとすぐに薄くなって、圧力差が大きく出ます。でも空気があまり入ってこないから、送風量は少なくなります。つまりこの「圧力差と送風量の関係」から、家の隙間の大きさがわかるんです。これが気密測定の原理です。
現場での測定は、専用の機械を窓に取り付けて行います。ラッパのような形のファンを窓に設置して、外に空気を出していきます。ファンの横にはいくつかコードが付いていて、1つは圧力を測るセンサー、もう1つは外気温と室温を測る温度センサー、そして流量を測るセンサーです。これらをコンピューターに接続して数値を導き出します。
気密性能を示す数値は「C値」と言いますが、これは「実測値」です。外皮平均熱貫流率(UH値)やQ値と違って、計算では出せない、実際に測らないとわからない数値なんです。つまり、家の性能を正確に知るには、気密測定が欠かせないということです。
測定には2つのタイミングがあります。1つは完成時、もう1つは中間測定といって工事中に測るタイミングです。僕のおすすめは中間測定です。なぜかというと、完成してしまうと中の構造が見えなくなってしまうので、仮に隙間があっても手直しが難しい。でも中間の段階なら、測ってみて数値が悪ければどこに隙間があるのかを特定し、修正することができるんです。実際に風の音がしたり、感触で漏れている場所がわかったりもします。
隙間がない気密の高い家は、なぜ大事なのか。それを説明する時によく例に出すのが「ストローでジュースを飲む」話です。普通にストローで吸えばジュースは飲めますが、ストローに針で小さい穴をいくつか開けると、ジュースは飲めなくなってしまう。穴から空気が入ってきて、吸う力が逃げてしまうからです。
住宅も同じで、隙間があると「計画換気」ができなくなります。3種換気や1種換気のシステムを導入しても、空気の流れがショートサーキットしてしまって、本来の換気ができなくなります。吸気口から空気が逆流したりすることもある。そうなると換気の意味がなくなってしまうんです。
さらに言うと、気密が高いと暖房効率もよくなります。ダウンジャケットで考えてみてください。いくら綿(羽毛)を詰め込んでも、風がスースー通ると暖かくならない。でも風を防ぐウィンドブレーカー1枚でも意外と暖かいですよね。住宅も同じで、気密がしっかりしていないと、断熱性能は十分に発揮されないんです。つまり、断熱だけでなく気密もセットで考えないと意味がない。
最近では「気密測定に立ち会った方がいいですか?」と聞かれることも増えました。僕としては、ぜひ立ち会ってもらいたいと思っています。人生で一度の家づくりですし、自分の目で確認できれば安心にもつながるからです。もちろんお仕事の都合などで難しい方には、しっかり結果をご報告しています。
現場としては、お客様が来られるとちょっと緊張もします。でもその緊張感が、より良い施工につながると思うので、ぜひ遠慮なくお越しください。そしてもし立ち会っていただけたら、ぜひ現場の大工さんや監督さんに「ありがとうございます」と声をかけてあげてください。めちゃくちゃ喜びますし、もっと頑張ろうという気持ちになります。
ということで、今回は気密測定について原理や意味をお話ししました。気密測定を通じて、より良い家づくりができることをぜひ知っていただけたらと思います。