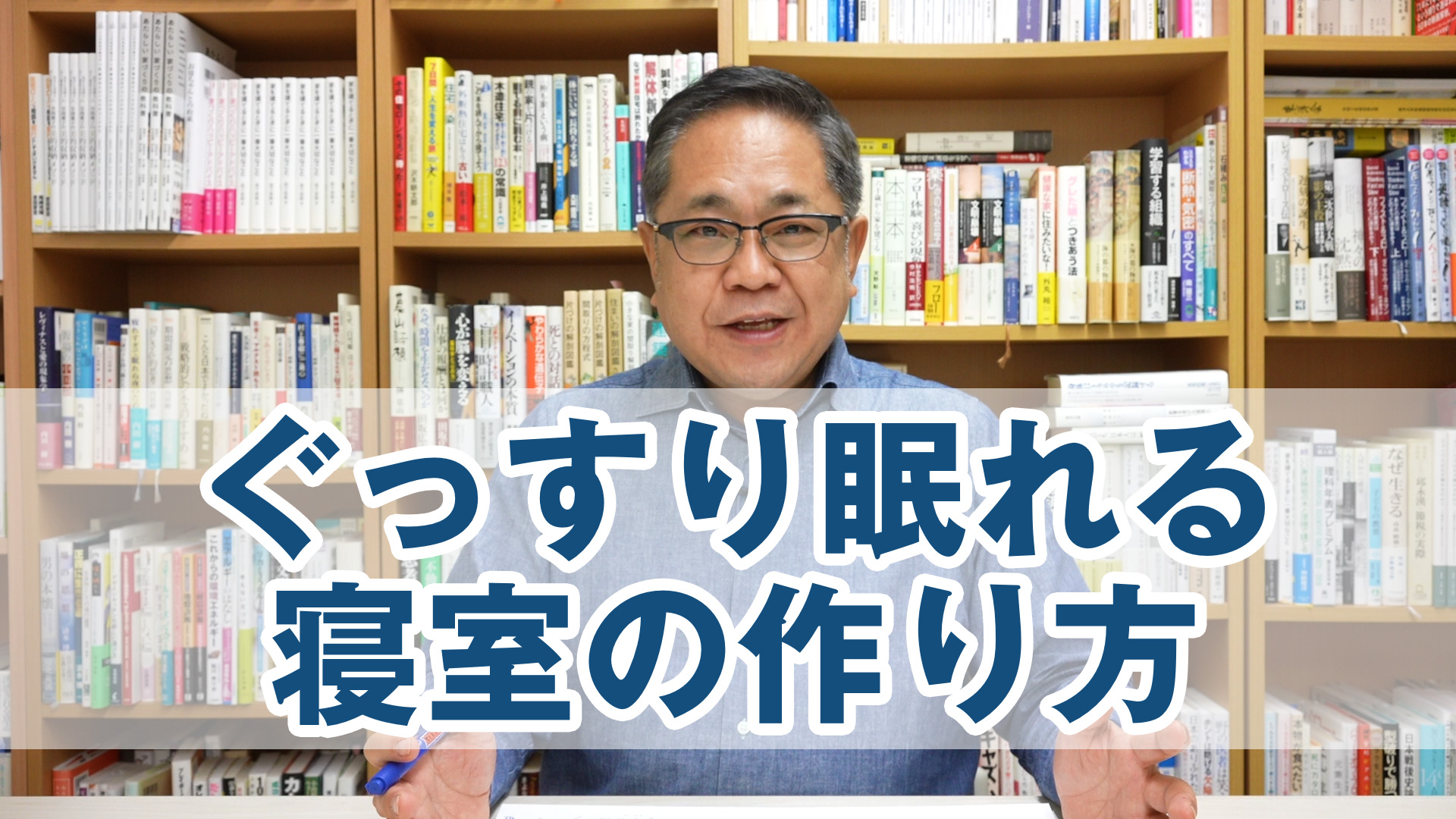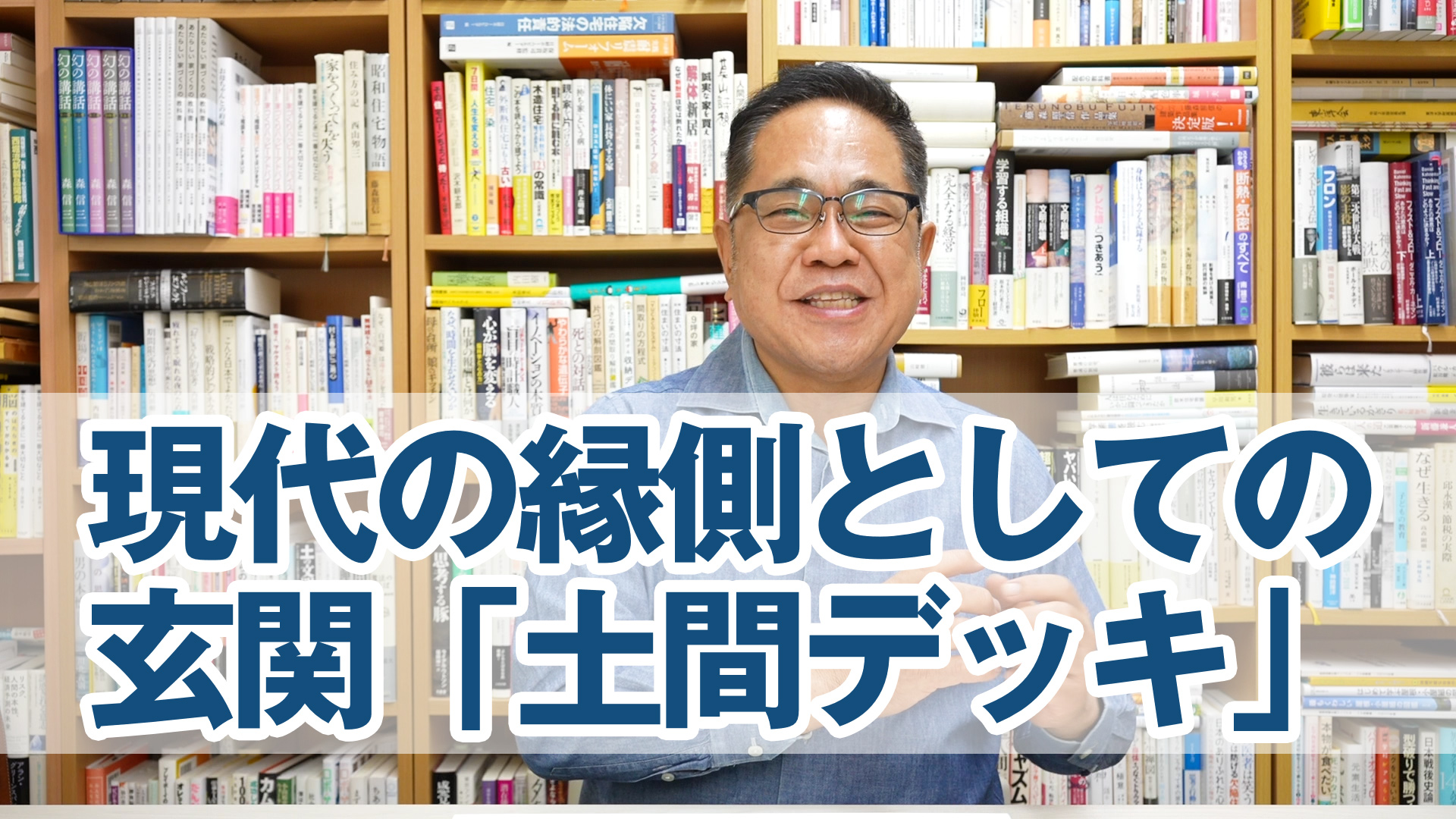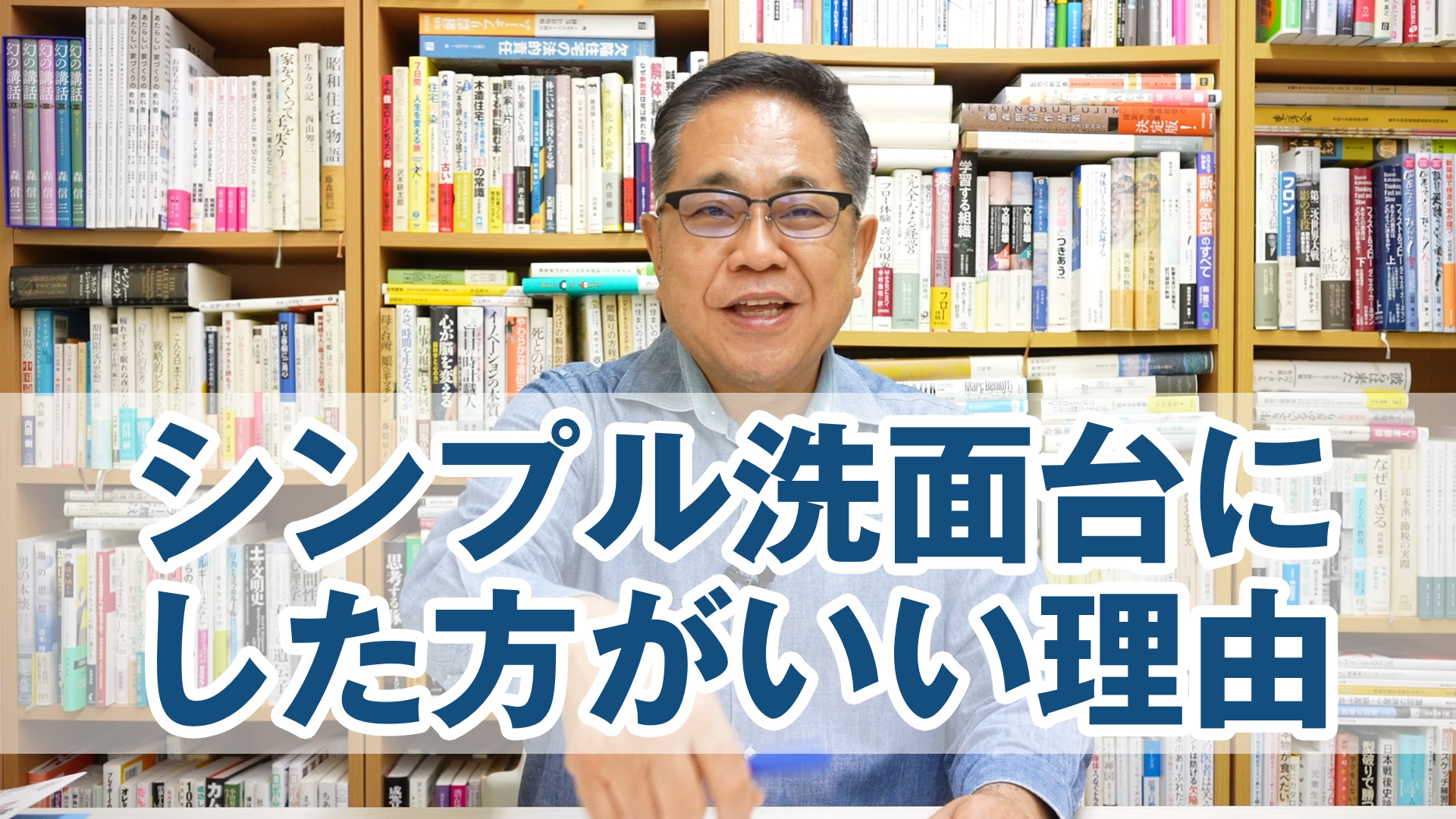住宅雑誌の間取りは参考になるか?を考える
今回は「住宅雑誌の間取りは参考になるか」について解説します。
先日あるお客様に「住宅雑誌にはたくさんの間取りが載っていますが、あまり見ない方がいいのでしょうか?」という質問をされました。私は「どうしてですか? 参考にすればいいんじゃないですか?」とお答えしました。詳しく伺うと、「これから家を建てるにあたって、たくさんのことを考えなければなりません。でも、住宅雑誌をたくさん見て、いろいろな素敵な家を知るのは楽しい反面、情報が多すぎて混乱してしまうのではないかと心配です。以前、賃貸住宅を選んだときも、たくさん調べて物件を見に行った結果、情報が多すぎて訳がわからなくなり、最後にはとても迷ってしまい、探すのが大変でした。家づくりでも同じことが起こったらどうしようと思っている」とのことでした。
その話を聞いて、私は率直に「すごい」と思いました。このお客様は過去の経験を踏まえて、慎重に家づくりを進めようとしているのだと感じました。もちろん、参考にすること自体は良いことですが、見るタイミングや、どのような視点で参考にするのかを知っておくと、より有意義に活用できるのではないかと思います。
家づくりの設計に関して、私が師匠と仰いでいる方は、松尾和也先生や、以前ご紹介した堀部先生、飯塚豊先生などです。飯塚先生は法政大学の建築学科で教鞭をとられ、学生に設計の基本を教え、鍛え上げている先生です。非常に論理的な思考でフローを組み立て、わかりやすく指導される方ですので、今回は飯塚先生のお話を参考にしながら解説していきます。
まず、飯塚先生は「家の設計をする時には2つの段階がある」とおっしゃっています。その1つが「事前の準備」です。一般的に家の計画を立てる際は、すぐ設計に入るイメージがあるかもしれませんが、設計に入る前の準備こそが非常に重要です。これは私たちプロにとっても基本であり、本当に大切なことです。
具体的にまず最初に考えるべきことは、これから建てる家の「構法」を決めることです。「構法」とは、建物の構造の形式を指し、木造・鉄骨・鉄筋コンクリートといった構造の種類や、断熱性能の仕様などが含まれます。このような部分は、ある程度プロの領域に関わる内容ですが、家づくりを進める上で最初に決めるべき重要な要素です。そして、同時に使用する素材についても決めておく必要があります。
多くの方は、「そんなことより、まずは間取りを考えたほうがいい」と思われるかもしれません。しかし、どういった構法で家を建てるかが決まらないままデザインや間取りを考えてしまうと、あとで大きなズレが生じる可能性が高くなります。飯塚先生はそのことをよく理解されているからこそ、まずは構法を決めるべきだと強く戒めておられます。
さらに、使用する素材に関しても先生は非常にこだわりを持たれています。特に「○○風」や「○○調」といった素材を避けるべきだとおっしゃっています。それらしく見せる仕様を選ぶのではなく、できるだけ本物の素材を選ぶことが重要だと先生は考えています。なぜなら家の寿命には「デザインの質感」や「素材の持ち」が非常に大きな影響を与えるからです。目先のコストを優先して「○○調」のようなフェイク素材を選んでしまうと、結果的に耐久性が低くなり、長持ちしにくい家になってしまうことがあるのです。
そして飯塚先生は、「類似事例を調べることが重要」とおっしゃっています。飯塚先生ご自身は過去にさまざまなスタディを行い、数多くの家の計画を立ててきた経験があり、その膨大な計画の控えがあります。それだけではなく、優れた建築家たちが過去に手がけた住宅の事例も多く存在します。そうした情報を収集し、活用することが家づくりに役立つということです。
さらに、家づくりのプロセスにおいて重要なのが「テーマを決めること」です。家づくりのテーマを明確にし、それと同時に施主の要望や必要な項目を整理しながら準備を進めていくことが大切です。この段階では、住宅雑誌に掲載されている間取りの情報を活用するのも有効な手段の一つだと考えられます。むしろ飯塚先生は、「事例を調べないのは時間の無駄になるので、必ず調べるべきだ」とおっしゃっています。したがって、適切に事例を活用することは、家づくりをスムーズに進めるうえで欠かせないポイントです。
ただし、単にたくさんの事例を集めればいいというわけではありません。大切なのは、「テーマに沿った事例を調べること」です。飯塚先生によると、家づくりのテーマには大きく分けて二つの要素があります。それが「敷地の特徴」と「施主の特徴」です。特に重要なのは「敷地の特徴」だとおっしゃっています。
施主はどうしても自分の好みや生活スタイルに合った事例を探したくなりますが、それよりも「建築予定の敷地に適した事例」を参考にすることの方が大切なのです。例えば、建築予定の土地がどの方角の何m幅の道路に面しているのか、向きはどうなっているのか、方位はどうか、隣の建物の大きさや高さはどれくらいかといった条件です。ただ漠然と「理想の間取り」を求めて住宅雑誌を見ていても、情報が多すぎて混乱するだけです。しかし、敷地条件に近い事例を探すという視点で情報を収集すれば、有益な参考資料となります。
また、現在どの程度の家財を所有しているのか、将来的にどのくらい増やす予定があるのかを考えながら、建物の大きさや形を決めていくことも重要です。そのうえで、適切な類似事例を選ぶことが求められます。仮に理想的な間取りの事例を見つけたとしても、自分が計画している家の広さが30坪なのに、その事例が50坪の住宅だった場合、実現できないと落胆してしまうこともあります。しかし、自分が50坪の家を建てることが可能な状況であれば、その事例を参考にするのは良いタイミングと言えます。
しっかりと事前に準備をし、自分の敷地条件に合った事例を活用することが、理想の家づくりへの第一歩となるのです。
飯塚先生はいろいろなことをおっしゃっていますが、ここで「間取り係数」という考え方について触れておきます。これは、吉田柱二さんが提唱されたもので、LDKと、それ以外の個室(子ども部屋や寝室など)の合計面積に「1.6」という係数を掛けることで、住宅全体の必要な面積がある程度算出できます。この1.6という数字は、吉田先生が長年の研究を通じて導き出した近似値のようなものです。この計算によって家全体の規模感が把握できるため、結果的に必要なおおよその予算も見えてきます。住宅のコストは建物の大きさに比例して変動するため、思っていたよりも費用がかかるとわかった時点で、規模の見直しが必要になることもあります。予算に制限がある中で、現実的ではないほど大きな家を望んでも、それは「絵に描いた餅」になってしまうため、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。こうして規模感やボリュームの想定をしながら、理想と現実のバランスを取っていくことが求められます。
また、家づくりを考える際に、もう一つ大切なのが「駐車場の計画」です。例えば、最寄り駅がなく、車が必須の生活環境であれば、家を考える前に駐車スペースの確保を優先するべきです。先に家のプランを決めてしまうと、後から駐車場を考えた際に、使い勝手の悪い「いびつなプラン」になってしまう可能性があるためです。そのため、「駐車場はどこに配置するか」「何台分必要か」といった点を、敷地条件と照らし合わせながら検討することが重要になります。さらに、方位による日当たりや周囲の景観なども、家づくりの条件として考慮すべきポイントです。例えば、敷地の北側に美しい景色が広がっている場合、北側にも大きな窓を設けたほうが良いかもしれません。こうした敷地ごとの特徴を生かした設計を考えることで、より満足度の高い住まいを実現できるのです。
このように、間取りの考え方、予算やボリューム感の把握、駐車場の計画、敷地条件の整理といった準備を整えたうえで、初めて住宅雑誌の情報が本当の意味で役に立つようになります。ただ単に雑誌を眺めて理想の家を探すのではなく、自分の敷地や条件に合った事例を参考にすることで、より現実的で実現可能な住まいの計画が立てられるのです。
ここからは設計に関してお話しします。飯塚先生は、まず最初にボリュームが決まったら、屋根をどうかけるかを決めるように言われます。その次に、中間領域という、外でもなく中でもない空間をどこかに作れないかを模索することを求められます。そして、窓の位置を整えることが重要です。窓の位置が決まったら、家の骨組みを合理的に組み立てます。これが一番きれいだという方法で進め、その後で間取りをそこに合わせていくという流れです。最後に間取りを作らないと、良い家にはならないということです。簡単に言うとこうなりますが、実際はとても難しいです。
多くの場合、私たちは敷地の特徴を整理し、規模の想定などを進めますが、できあがった時にすぐ間取りを考え始めると、行ったり来たりしてしまい、「間取りは作ったけれど何となく格好が悪い」「外観がいまいちだと感じる」「中間領域が全く取れていない」といったことが起こりがちです。こうした問題は避けるべきです。このような流れを守ることが、王道だと思います。
そのため、「住宅雑誌の間取りを参考にしない方がいいのか?」という問いに対しては、前段階が終わっていない状態でいきなり間取りの情報を集めると、混乱してしまうことがあるとお伝えしたいです。なので、まず最初は「木造の家でこれぐらいの断熱性が必要」「素材はどんなものを使うべきか」というテーマやボリューム感を少し曖昧にしながら考え、その後で間取りを考えるのが良いと思います。
人間というのは不思議なもので、ダラダラと何も考えずに見ていると、目に入るものには気づきませんが、ある枠組みで探し始めると、それに近いものが自然に目に入ってくることがあります。テーマや条件が整理できていると、目指しているものが自然に入ってきます。住宅雑誌の間取りを参考にするのは、家づくりに本気で取り組む時にとても良い方法だと思います。ただ、パラパラと住宅雑誌を見て「これ、良い家だな」と思うのは楽しいので、それを娯楽として楽しむのは全く問題ありません。でも、本当にここで決めなければならない時には、順番が逆になると、少し時間の無駄になってしまう可能性があると思います。ぜひ参考にしてください。