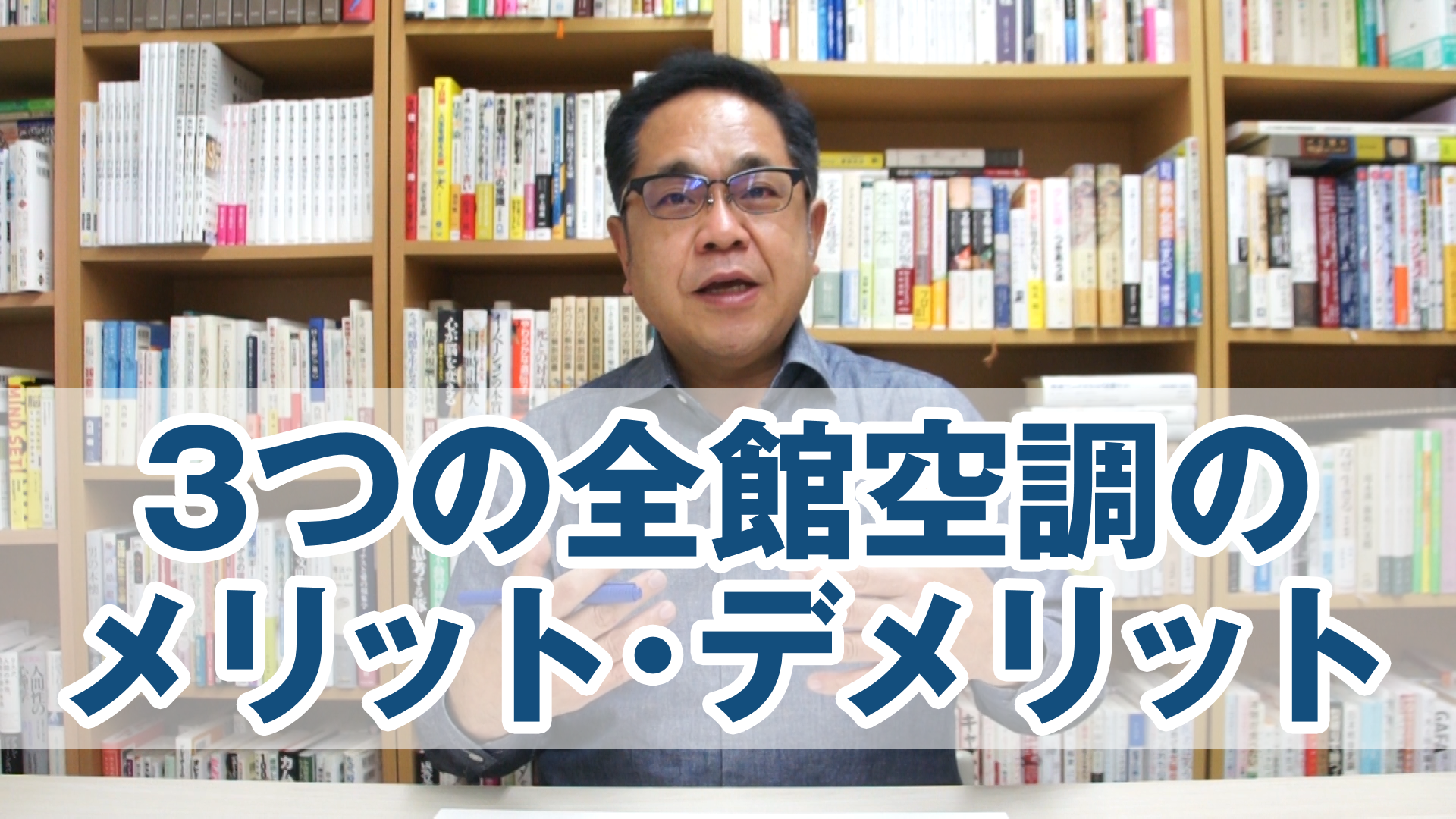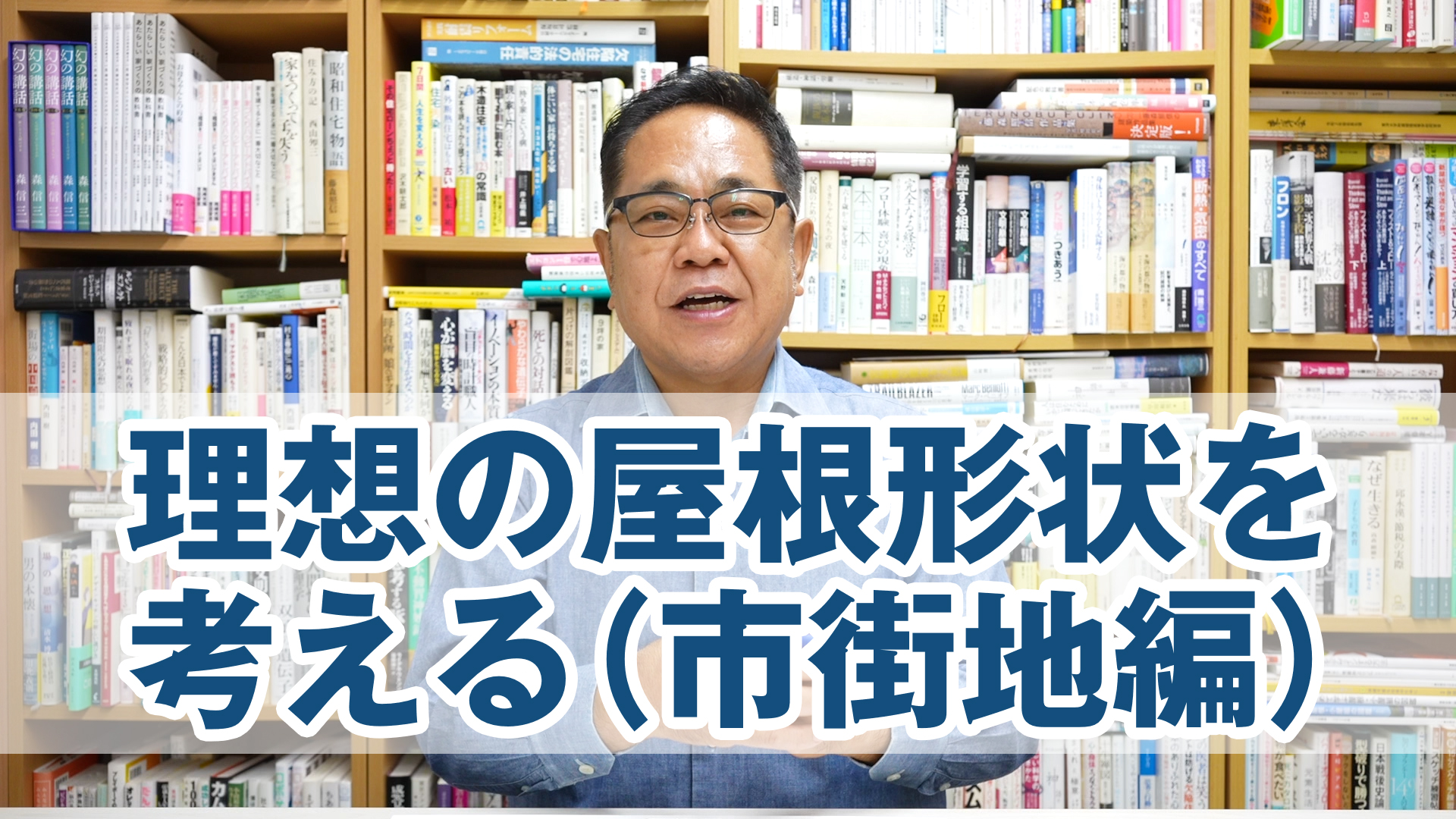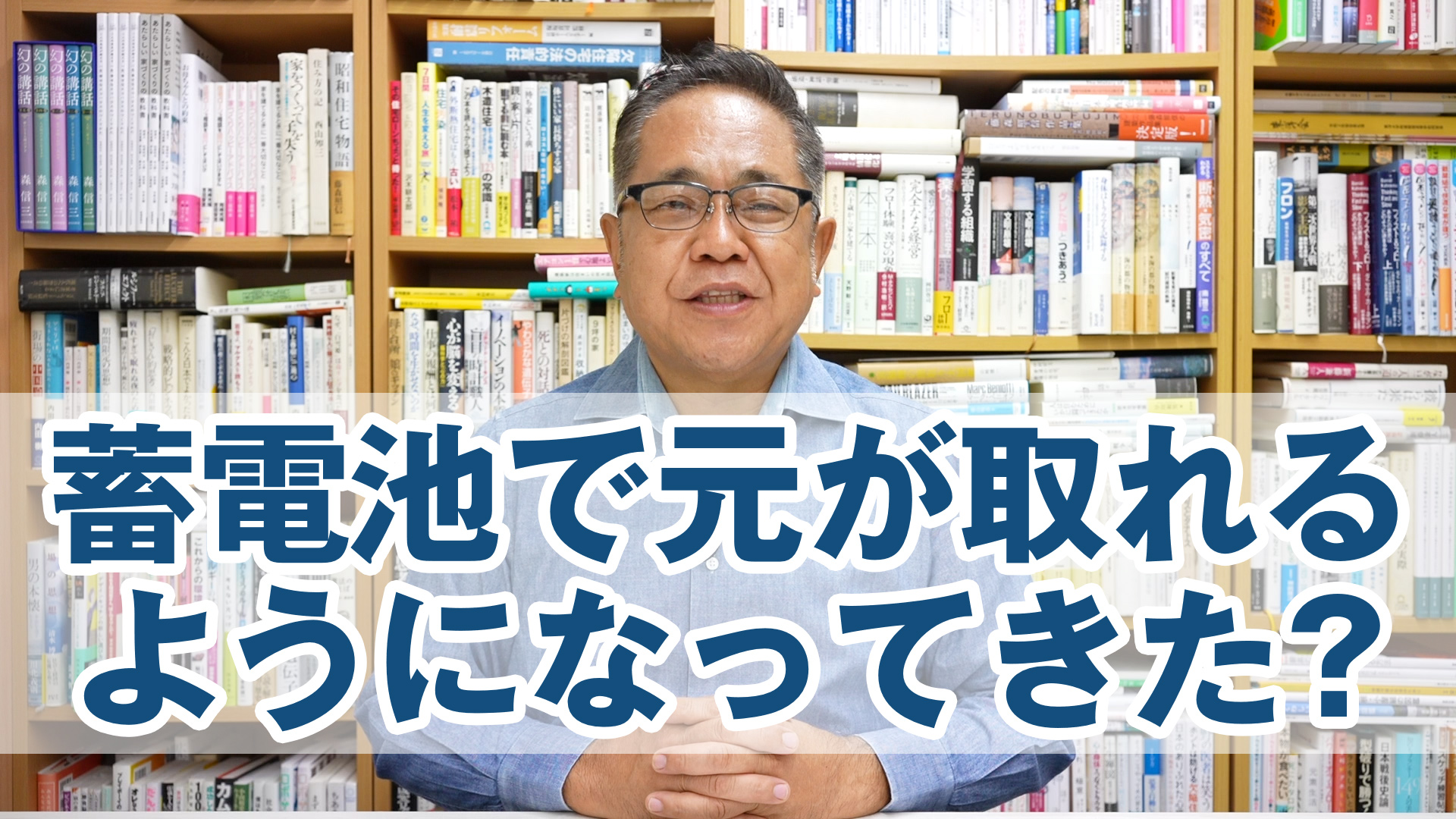「60歳のトリセツ」を読んで終の棲家を考えた
今回は『60歳のトリセツ』という本について、家づくりに絡めてお話しします。
この本は、以前にも「トリセツシリーズ」を執筆されている黒川伊保子先生によるものです。黒川先生は、脳科学や人工知能の専門家であり、この本はシリーズの続編のような位置づけになっています。私がこの本を読んだきっかけは、YouTubeで武田鉄矢さんがこの本を解説されていて、自分ももうすぐ63歳だから読んでみようかなと思い手に取りました。そして、読んでみると、なかなかの衝撃を受けました。
この本の冒頭で、黒川先生は「60歳の脳スイッチングを済ませましたか?」と問いかけています。私はすでに60歳を過ぎていますが、「スイッチング?」と戸惑いました。どういうことかというと、日本人の多くは「正しく生きること」を目指しているというのです。黒川先生の定義による「正しさ」とは、健康で、頭の回転が速く、美しく、スタイルや運動神経、センスも良く、さらに思いやりや情熱、ユーモアがあることを指します。そして、それに沿って生きるべきだと考えてしまう。私はこの定義にあまり当てはまらないので、この時点で少しドキドキしました。
では、なぜ多くの人が「正しさ」を求めて生きているのでしょうか?これは日本人に限らず、世界中の人類が持つ本能によるものだと黒川先生は述べています。その本能とは「生殖」のためです。命を育み、繁栄していくためには、異性に選ばれなければなりません。そのため、人は愛され、尊重される生き方を目指すようにできている、というのです。
ここで黒川先生の素晴らしい点は、「子どもを持つ・持たない」という話に単純化されるのではなく、より広い視点で語られていることです。人は「子どもを持たなければならない」と言っているわけではなく、事情により持たない選択をする人もいる。そのような人々は社会にとって非常に重要な存在だと述べています。なぜなら、子育てには莫大なエネルギーが必要です。そのため、子どもを持たない人は、時間・お金・意識・労力といった人生の資源を、社会のために使うことができます。そういう人がいるからこそ、社会は成り立っているのです。
さらに、脳科学の観点から見ると、人間の脳は生殖本能に強く突き動かされている一方で、人間の子どもは他の動物に比べて非常に弱い存在です。歩くまでに1年かかり、数年間は母乳を飲み続け、さらに子育てには多くの苦労が伴います。そのため、人間は単独で子育てをするのではなく、共同体として育てる必要があります。こうした背景から、人間は仲間外れにならないように行動し、群れの中で評価されることを求める生き物なのです。
しかし、60歳という年齢になると、ほとんどの場合、生殖活動からは卒業します。すると、50代までの価値観に縛られることは、自分自身にとっても、周囲の若い世代にとっても良くない影響を及ぼします。例えば、私自身も若い人に「子どもはどうなの?」と不躾に聞いてしまったり、自分の価値観以外のものを受け入れられなかったりすることがあります。しかし、それは良くないことなのです。
この本を読んで、まるで叱られているような気持ちになりましたが、黒川先生は、「50代までの人生と60歳からの人生では、脳の生きる目的が違う。だからこそ、スイッチングしなさい」と説いています。私も60歳を迎えて1年以上が経ちましたが、この言葉をしっかり胸に刻まなければいけないと感じました。
この本は、全六章で構成されています。第一章のテーマは「若さを気にする感覚を捨てなさい」。特に女性にとっては、少しドキッとする内容ではないでしょうか。第二章は「ボケを気にするのも捨てなさい」。最近は物忘れが気になることも多く、自分も少しボケてきたと感じることが増えました。
第三章は「子どものことを気にするのはやめなさい」。これまで一生懸命子育てをしてきた親にとって、子どものことを気にかけるのは自然なことです。私自身も、最近娘が社会人になり家庭を持ちましたが、それでもまだ子どものことを気にしてしまいます。そして特に私の心に響いたのは、第四章と第五章でした。その前に、第六章では「友を気にすることを捨てなさい」と書かれています。女性は男性に比べて、友人関係を気にする傾向が強いと言われますが、60代になると、それが必ずしも良いことではないと指摘されています。
そして、私が最も衝撃を受けたのが、第四章と第五章です。第四章は「老いと死を気にすることを捨てなさい」。これは男女を問わず誰にでも関わるテーマです。特に年齢を重ねるにつれて、どうしても避けられない問題ですが、それを過度に気にすることなく、どのように前向きに生きるかを考えさせられます。
しかし、私が最も驚いたのは第五章の内容でした。そのテーマは「夫を気にするのを捨てなさい」です。「夫を捨てる?!」と思わず声を上げそうになりました。この章では、夫婦関係について非常に大胆な視点が提示されており、読んでいて本当に衝撃を受けました。興味のある方には、ぜひこの本を手に取って読んでいただきたいと思います。60歳からの生き方に関するヒントや知恵が、ぎっしりと詰まった一冊です。
黒川先生は、「人間は7年ごとに1回脱皮する。その節目ごとに、年代に応じた脳の賞味期限のようなものがあり、新たな成長の段階を迎える」とおっしゃっています。まず生まれてから7歳、次が14歳、21歳、28歳…そして63歳というように、7年ごとに人生からの挑戦があるという考え方です。
この話を少し詳しくご紹介すると、まず7歳までに大脳に対してオートマチックに動作を支援する小脳が完成します。次に14歳になると、感性が完成します。その人にとって美しいもの、嬉しいこと、悲しいことといった感情の基盤が形成される時期です。この本の中でも「60歳になったら、14歳の自分にもう一度会いましょう」という素敵な提案がされています。
そして21歳になると、前頭葉が完成します。前頭葉は、難しいことを考える役割を担う部分です。28歳では「入力性能」が最大になります。つまり、情報をどんどん取り込み、蓄積する力がピークに達する時期です。ただし、逆に言えば、ここから少しずつ衰え始めるとも言えます。
黒川先生は20代前半の頃、仕事で行き詰まったときに、尊敬する先輩に相談したそうです。すると、その先輩は「四の五の言わずにやれ」と言ってくれたそうで、その言葉がとてもありがたかったとおっしゃっています。つまり、28歳まではとにかくがむしゃらにやるべきだということです。
そして、28歳を過ぎると、人は必ず立ち止まる瞬間が訪れます。黒川先生は、これを「30歳のインスピレーション」とおしゃれな表現で表しています。
次に35歳。ここでは「迷いと戸惑い」が生まれる時期だと言われています。例えば、20代の頃は勢いで思い切った決断ができたことも、30代半ばになるとさまざまなことを考えるようになるのです。これは脳の構造的に自然なことです。結婚に関しても、20代ではあまり深く考えずに踏み切れたことが、35歳を過ぎるといろいろな事情を考慮するようになるのも、この影響かもしれません。
42歳になると、「物忘れの40代」が始まると言われています。確かに思い返すと、そうかもしれませんね。しかし、40代から高まる能力が「気づき」です。この「気づき」の力が高まることで、若い人の悩みを「なるほど、こういうことを考えているのか」と理解できるようになったり、年上の先輩方の気持ちにも共感できるようになったりします。そして、この「気づき」のピークを迎えるのが56歳です。この頃には、誰もが何かのジャンルで達人になっていると黒川先生は言います。確かに長年の経験を積んできたことで、自然と身についたものは多いはずです。
しかし、脳のピークはここで終わりません。63歳になると、「人生の達人」になると言われています。特定のジャンルの達人を超えて、人生そのものを俯瞰し、広い視野を持てるようになるということです。もうすぐ63歳になる私としては、そう言われると少し自信がない気もしますが、それでもこの考え方には勇気をもらえます。
黒川先生は、「60歳になったら若い脳にも敬意を払わないといけない」ともおっしゃっています。28歳の頃の自分を振り返ってみて、「あの頃の自分はがむしゃらに頑張っていたな」と思うことがあるでしょう。そんな自分を抱きしめてあげるような気持ちを持つことが大切なのです。
さらに驚くべきことに、80歳になっても人は成長すると言います。80歳だからこそ見えてくる境地があり、そこから新たな学びを得ることができるのです。この話を聞くと、「年を取った」なんて言っていられないなと感じます。人生はまだまだこれからと思わせてくれる前向きな考え方です。
少し前向きになっている私に対して、「夫を気にすることを捨てろ」という言葉が響きました。ここで、武田鉄矢さんが紹介していたエピソードを交えてお話ししたいと思います。武田鉄矢さんが語った話の中に、「おじいちゃんとおばあちゃんには、家庭生活を運営する能力において、圧倒的な差がある」というものがありました。これは、社会性や頭の良し悪しの話ではなく、単純に「家庭を切り盛りする力」の違いを指しています。
武田鉄矢さんが紹介していたのは、ある経済界の重鎮と言われる経営者が引退後に奥さんに怒られた、というエピソードです。ある日、奥さんから「あなた、ゴミを出してきて」と頼まれたそうです。その経営者は朝早くにゴミを出しました。しかし、その後、奥さんにものすごく怒られたのです。なぜ怒られたのか?その理由を聞くと、「あなたはゴミ出しの最終工程しかやっていない」と言われたそうです。
黒川先生の別の本でも紹介されていましたが、「ゴミ出し」と一口に言っても、実は8つの工程がある。しかし、その経営者がやったのは、最後の「出す」というたった1つの工程だけ。しかも、出す時間が早すぎたため、カラスに荒らされ、ゴミが周囲に散らばり、近所の人たちに迷惑をかけてしまったのです。その結果、奥さんから「ゴミを出したら、ちゃんとネットをかけなきゃダメでしょ。しかも、カラスに荒らされないように、しっかり掛け方を考えないとダメでしょ。そんなこともわからないの?」と怒られ、「あなた、ゴミもまともに出せないの?」とまで言われたそうです。
経済界の重鎮だった人が、家庭ではそんな風に叱られるとは、なかなか衝撃的な話ですね。さらにある日、その方が早めに帰宅し、シャワーを浴びたらまたしても奥さんに怒られたのです。理由は、「鏡についた水滴をちゃんと拭かなかったから」。
経営者は「ただシャワーを浴びただけなのに、なんでそんなに怒られるんだ」と思ったそうです。しかし、奥さんの言い分はこうでした。「鏡についた水滴をそのままにしておくと、水垢になって落ちにくくなるのよ。掃除の手間が増えるのよ。ちょっと拭けば済むことなのに、なんでそんなことがわからないの?」
家庭を完璧に回すために、奥さんは日々細かいところまで気を配っている。そんな彼女からすると、経営者がやっていることは「余計な仕事を増やしている」ように映ったのでしょう。この話を聞いて、やはり家庭を回す能力というのは、経験と気配りの積み重ねなのだと改めて感じました。
仕事ができる人でも、家庭ではまた違ったスキルが求められる。そんなことを考えさせられるエピソードでした。
56歳になると、ある領域の達人になると言われています。特に60代の人たちは、専業主婦で、旦那さんが外で働くというライフスタイルを送ってきた方が多い世代です。こうした背景の中で、奥さんは長年の経験を積み重ねた「家事の達人」となっています。一方で、60代になった旦那さんは、これまで仕事に専念してきた分、家事に関してはまるで「新人」です。つまり、長年積み重ねた技を持つ奥さんと、まったくの初心者である旦那さんが、同じ家庭の場にいることになります。そうなると、当然ながら奥さんの視点からすると、旦那さんの振る舞いにイラッとすることも増えるようです。つまり私もこれから奥さんに怒られることが増えるのかもしれないなとドキドキします。
そもそも、夫婦というのは、生物学的には「生殖」という第一の目的のために結びついたユニットです。その観点から見ると、黒川先生は「人は自分と真反対のタイプをパートナーとして選ぶものだ」と言っています。例えば、自分が得意なことと、相手が得意なことが違うことで、お互いを補い合い、生存確率が上がる。だからこそ、元々は「一緒にいるのが向かない相手」とペアリングして、子どもを産み、育ててきたのだと。しかし、60代になり、生殖の役割を終えたとき、夫婦の関係は「ゼロクリア」の状態になる。そんな中、イラッとしやすい関係にある二人なのに、さらに家事のベテランと新人という立場の違いも加わることで、奥さんが旦那さんに対して「イライラするのは宿命的なもの」だと黒川先生は言っています。だから、女性は「旦那にイライラするのは当たり前のことなのだ」とまず理解することが大事だという話でした。しかし、これを聞いている私はドキドキしてしまいますね。
そして、黒川先生がこの話の最後に出した例えが、まるでハンマーで殴られるような衝撃的なものでした。それを聞いたとき、本当に胸にズシンと響きました。ハウスメーカーの宣伝では、こんな提案をよく見かけます。「シニアが暮らす理想の住まいとは、お互いの姿が自然に目に入り、同じ空間にいながらも適度な距離感を保てるリビングが理想的です」といったものです。しかし、黒川先生はこの考えをバッサリと切り捨てています。奥さんからすれば、旦那さんの姿が少しでも視界に入ると、それだけで疎ましく感じるもの。だからこそ、本当に女性にとって必要なのは、「旦那の姿が見えないリビング」なのだと。そんな話を聞いたとき、私は思わずえっ?と驚きました。
これを聞いて、私はふと考えました。私は家づくりに関する相談の場で、シニアの方々に「こんな感じのリビングダイニングはいかがですか?」と提案してきました。でも、この話を聞いた瞬間、背筋が寒くなりました。「自分の提案、間違っていたのかも」と。正直、少し落ち込みました。しかしさらに読み進めることにしました。まず大切なのは、夫婦のプライベート空間を確保すること。つまり、時間と空間の分離を意識しないといけません。なぜなら、もともと夫婦は「一緒にいることが向かない間柄」だからです。生殖プロジェクトが終わった今、違和感があるのは当然のこと。でも、一緒に暮らしていく以上、夫婦の間には愛着が必要です。しかし気配を感じる距離感は大事なのです。お互いを慈しみ合うためには、ただ同じ空間にいるのではなく、適度な距離を持つことが重要なのです。
そして、さらに衝撃的だったのは「女性の声には賞味期限がある」という話です。恋に落ち、一緒に生殖活動のプロジェクトを頑張った。でも、60歳になって「ゼロクリア」されたら、その賞味期限は終わっているのだと。そんな相手に対してムスッとした態度をとるのはどうなのか、と問われます。
思い返せば、かつて大好きだった彼女と目が合ったとき、私はニコッと笑っていたはずです。せめて目が合ったときくらいは微笑むべきなのではないか。夫婦の愛着がゼロになっているなら、そうした習慣を作らないと、ますます絆が薄れてしまうのです。
そして、もうひとつ大切なのは、旦那さんに対する接し方。「男というのは、物事の是非をつけたがる生き物。でも、夫婦にとって大事なのは、物事の正しさよりも、妻の気持ちなのよ」と黒川先生は言います。
私も女房から何か相談をされたとき、つい問題解決をしようとしたり、アドバイスをしてしまうんです。でも、妻が本当に聞きたかったのは気持ちであって、問題を解決しようというのは男性の思い込みなんだと思います。男性は、どうしても表面的な部分だけを見てしまう傾向があります。
例えば、妻が話している内容に対して、表面的な言葉そのものに反応しがち。でも、女性はそれを超えて、言葉の裏にある本当の気持ちを感じ取ろうとするセンサーがすごく敏感です。そのため、何気ない一言でも、裏に何かがあるのかと深く考えたり、察しようとしたりします。
例えば、晩ご飯のおかずを見て「今日のおかずはこれだけ?」と聞いてしまうことがあります。自分では特に深い意味を込めていないのに、これが妻には不満を感じさせてしまうんです。こういうシンプルなつぶやきにも、意図せず過剰な反応をされて、逆に私が萎縮してしまうということがよくあります。こうしたことは、日常生活の中で多くの場面で展開されているんだなと思います。
これは、決して男性だけが悪いわけでも、女性だけが悪いわけでもなく、お互いに気を使いながら生活していくことが大切だと感じています。
そして、ここからうまくやるための知恵が第五章に書かれていますが、私自身、対の住処というテーマは難しいと思いました。相手や家族の気持ちに寄り添いたいと思いながらも、もし私の妻が「あなたは疎ましい」と言ったとしても、きっと「そんなことないよ」と言ってくれると思います。しかし、実際には疎ましく感じる日もきっとあるはずです。
家族全体についても、飯塚先生がよくおっしゃっているように、家には「いつでも一緒にいられる安心感」と「いつでも一人になれる安心感」の両方が必要だと感じます。自然にお互いに理解できる空間がなければ、本当に大切なことが欠けていると感じます。
私も他の動画で言っていたように、男性には書斎が必要だと言っていましたが、女性にとってもリビング以外の居場所が必要だということを真剣に考えなければならないと思います。対の住処がうまくいかないと、非常に問題です。
これについては、私の懺悔のような話ですが、家づくりに関わる者として、過剰に反応してしまった部分もあるかもしれません。生殖期間が終わった夫婦には、命に関わるような直感的なぶつかり合いはもう必要ないと言われています。だからこそ、奥さんに二度惚れさせることが重要で、それが60歳を迎えた男性としての嗜みだと感じています。
第六章では、男性が男同士で集まる理由や場を作ることについて話されていますが、女性は会いたいから会うということが強いと言われています。そのため、時には「会いたくない時も友達として会うこと」があり、そうした時に自分の気持ちを率直に表現できる場が必要だと感じます。
これらは、60歳になった男性、女性共に見習うべき点だと思います。私の周りにも、次の住処に関してリノベーションや建て替えを考えている方が多いため、工務店の立場からは少し外れるかもしれませんが、このようなことを意識して考えると、脳のピークを迎える60代を共に謳歌できる住まいができるのではないかと思います。
最後に、うちの奥さんに謝りながら、この話を締めくくりたいと思います。ぜひ参考にしてください。