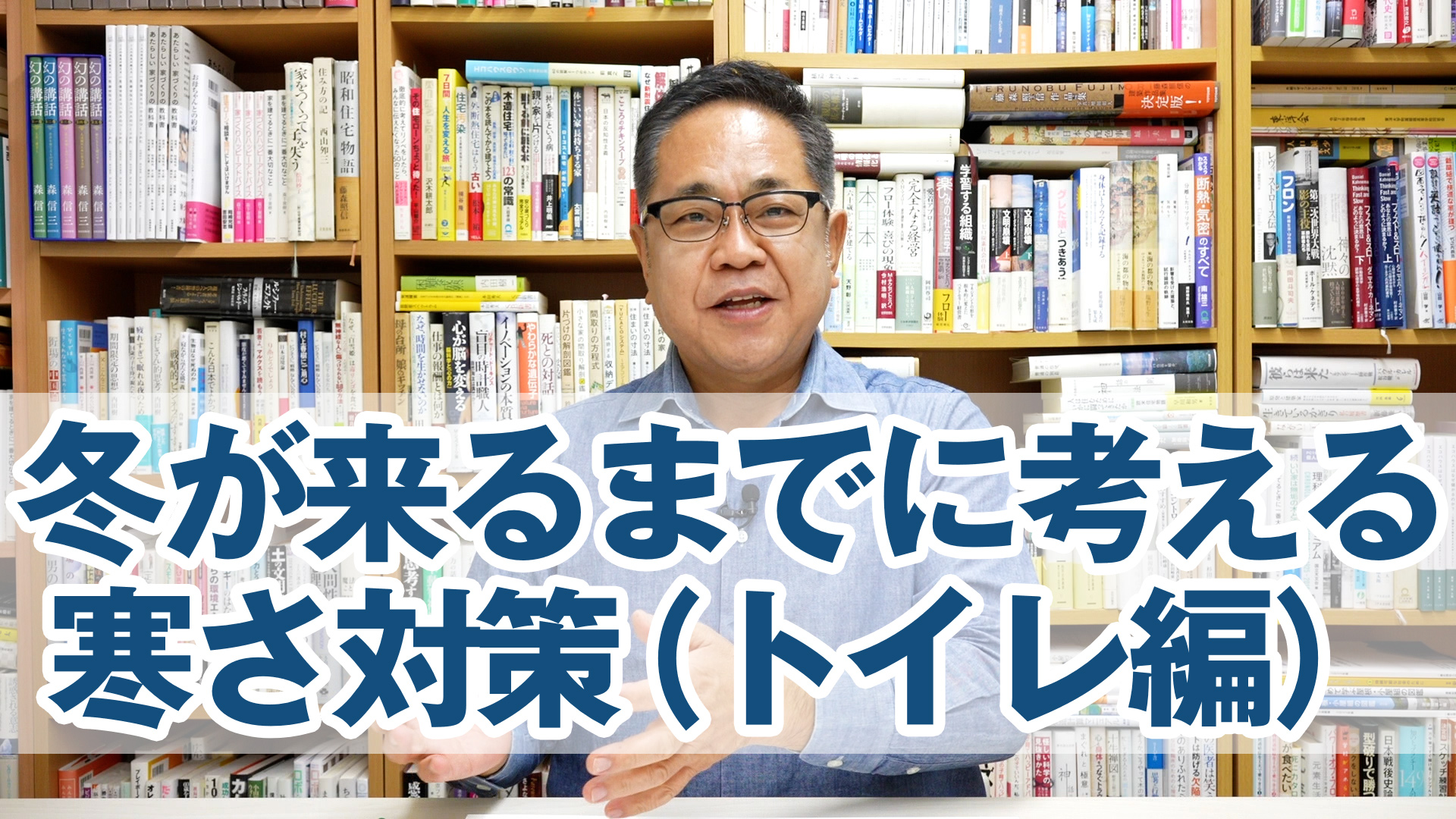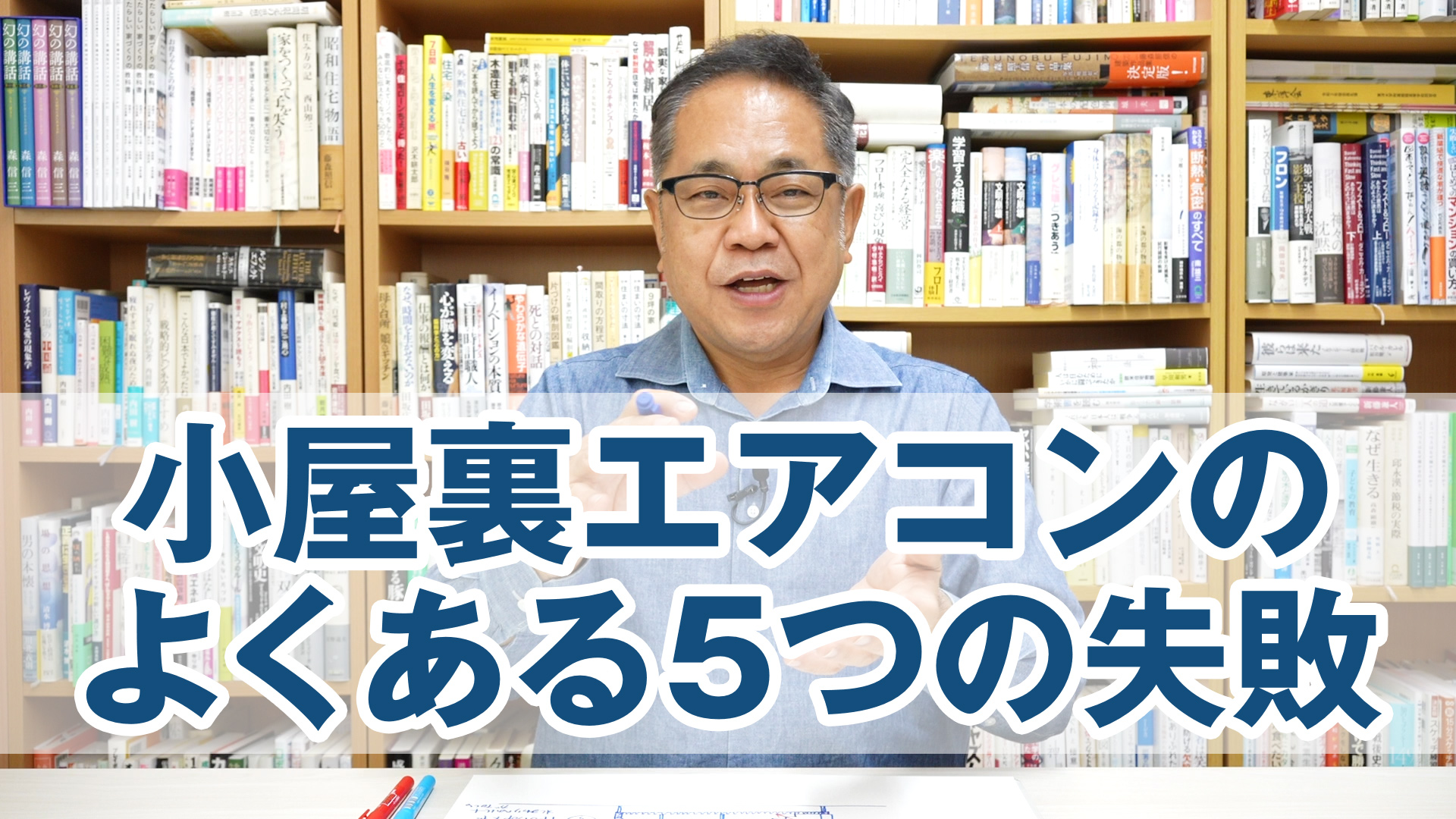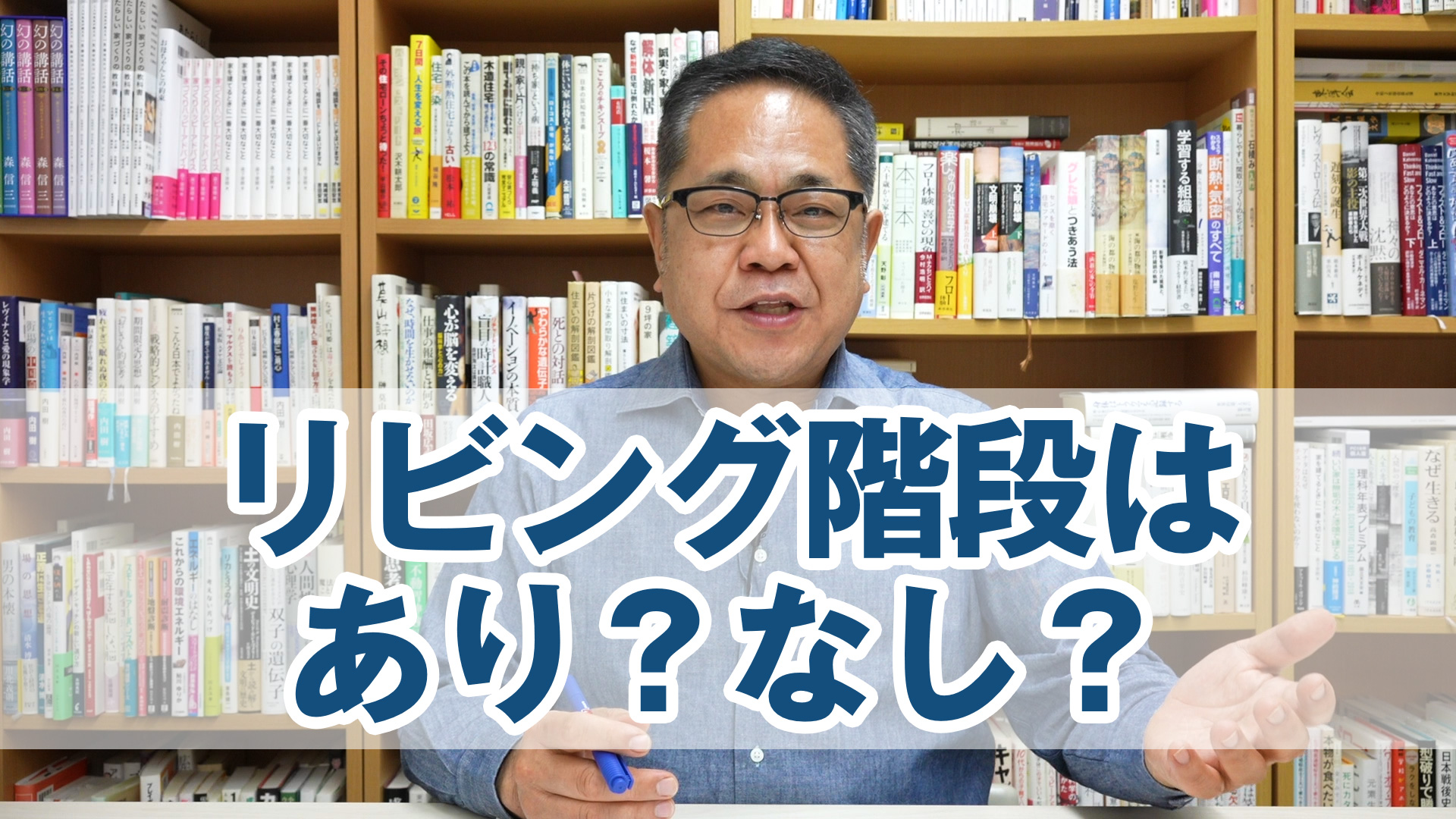2025年建築基準法の改正で家づくりはどう変わるのか?
こんにちは、モリシタ・アット・ホームの森下です。
今、建築の世界ではちょっとざわついています。その理由は、2025年4月から建築基準法の一部が大きく変わるからです。今回はその改正内容について、僕の板書を使いながら解説していきたいと思います。
そもそも、建物を新しく建てるときや、大規模なリフォームをするときには、「確認申請」を出して審査を受け、法律に適合しているかどうかを確認してもらう必要があります。これまでもその仕組みはあったのですが、今回の改正で、その審査の内容が大きく変わることになりました。
木造の新築住宅については、これまで「2号建物」と「4号建物」という分類がされていました。ざっくりいうと、3階建てや大きな建物が「2号建物」、それ以外が「4号建物」とされ、4号建物については「構造計算書を省略してもいいですよ」という“4号特例”が認められていました。つまり、設計者がしっかりチェックしているという前提で、構造に関しての詳細な審査は行わなくてもよかったわけです。
ですがこの特例には問題点もありました。本来、耐震性などの安全性が確保されているかを確認する必要があるにもかかわらず、「特例だから」ということで、確認申請のスピード重視になっていた面があったのです。その結果、一部の設計では、お施主さんの希望を優先しすぎて、安全性に疑問が残るケースも出てきてしまいました。
そういった背景から、今回いよいよ「4号特例は廃止します」という方針になったわけです。つまり、これからは2階建ての住宅であっても、しっかりと構造の審査を受けなければならなくなります。唯一、構造審査が免除されるのは「平屋で200㎡以下」のケースだけです。
これにより、確認申請の手続きが変わります。建築主と設計者は、これまで通り「確認申請」を出すだけでなく、「省エネ性能の適合性判定」「構造の適合性判定」も一緒に提出する必要があります。これらの審査は、行政や登録機関によって行われますが、実務的には民間の審査機関が担当することが多いです。
ただし、同じ機関でも部門が異なるため、確認申請は通っても、構造や省エネの審査が終わっていなければ着工できない、という状況が起こり得ます。結果的に、確認が下りるまでの期間が延びることになりますし、審査費用もかかってきます。
これはお施主さんにとっても設計者にとっても、新しい負担になりますが、同時に「安全で性能の高い家を建てるための大きな一歩」でもあると思っています。住宅は一生使う大切な資産ですから、その安全性や快適性がより確かなものになるという点では、歓迎すべき改正だと僕は思っています。
一方で、リフォームの現場では、もう少しややこしい問題も出てきます。例えば、間取りの変更をともなうリフォームで構造に手を入れる場合、今後は新築と同様に確認申請が必要になります。さらに、工事中に図面と違う構造が見つかった場合などは、申請内容を変更する「変更申請」が必要になることもあります。
こうなると、工期が延びる可能性もありますし、追加費用が発生するケースも出てきます。ただ、それでも安全性が高まるのであれば、ある程度の手間やコストは仕方ないとも言えます。重要なのは、お施主さんと設計者、工務店がしっかり信頼関係を築き、柔軟に対応できる体制を整えておくことだと思います。
今回の改正は、日本の家づくりが「長く大切に住み継がれる住宅」に変わっていくための、大きなターニングポイントだと僕は感じています。これまでのように、「建てては壊す」ではなく、100年、200年と住み継がれていく家を目指していく。そんな時代の流れに向けて、僕たちも本気で取り組んでいかなければならないと感じています。
というわけで、今回は建築基準法の改正について解説しました。これから家づくりをされる方、あるいはリフォームを考えている方にとっても、きっと参考になる内容だったと思います。ぜひ、じっくりと時間をかけて、安全で快適な家づくりを進めていただけたらと思います。