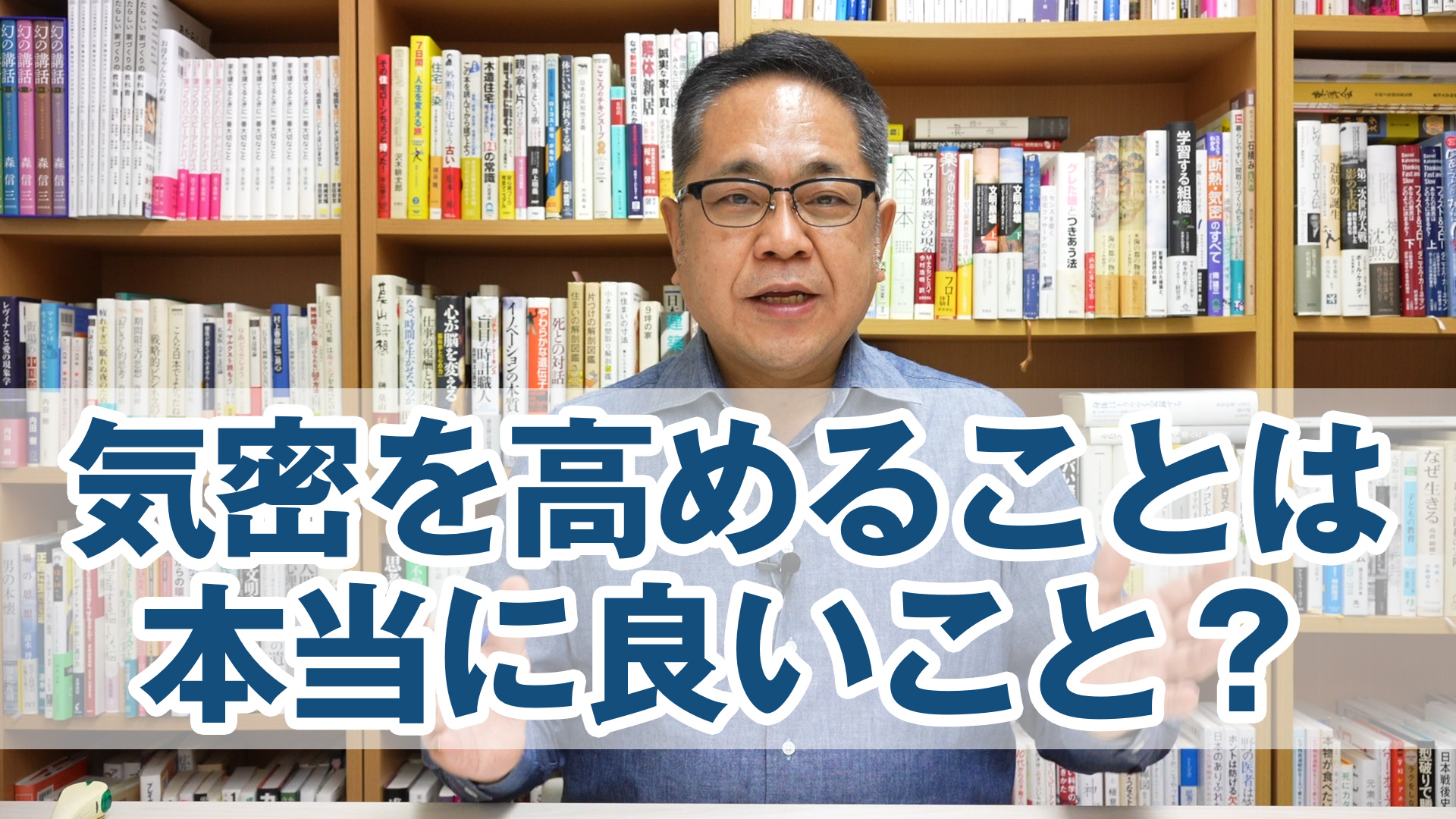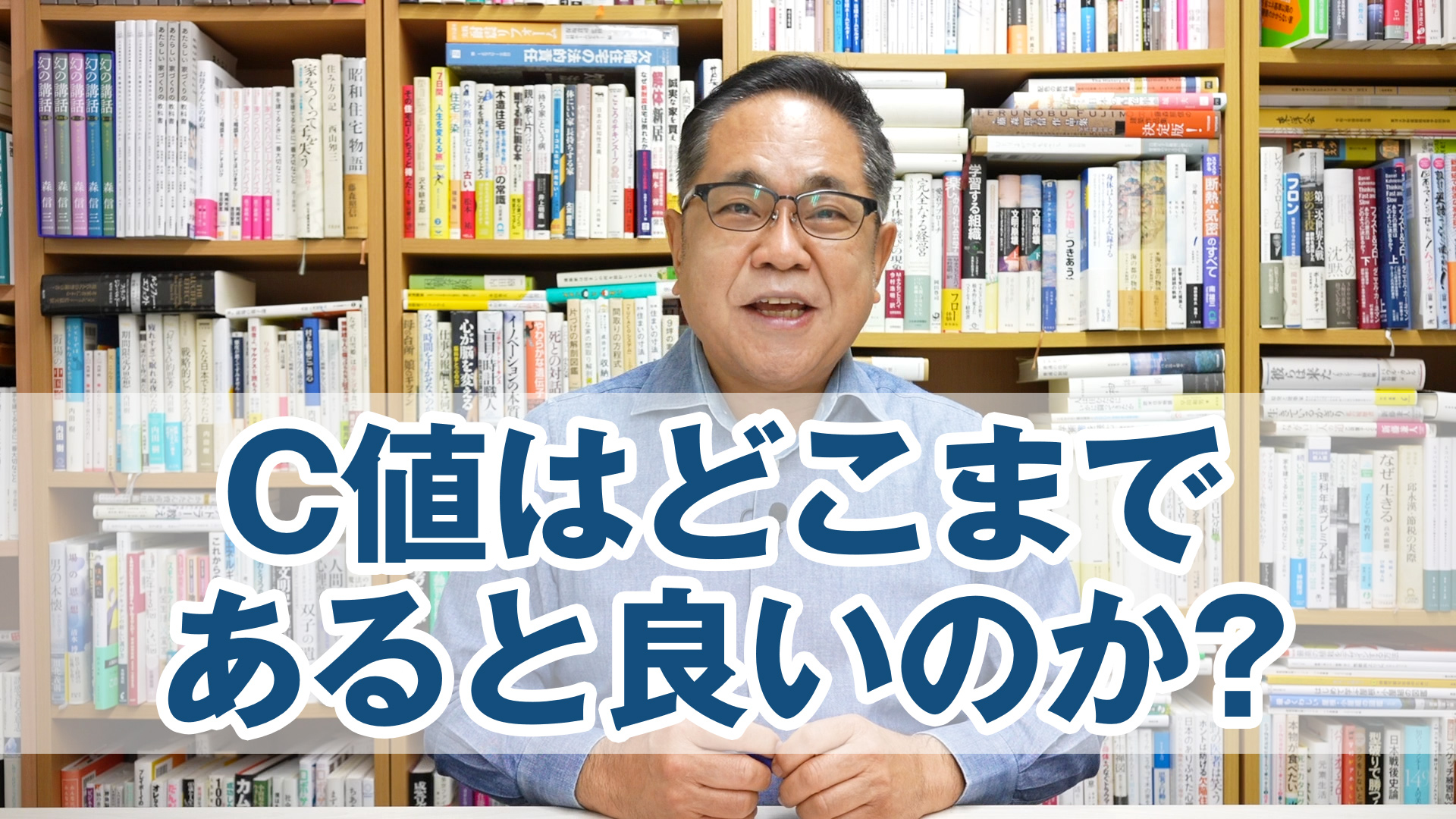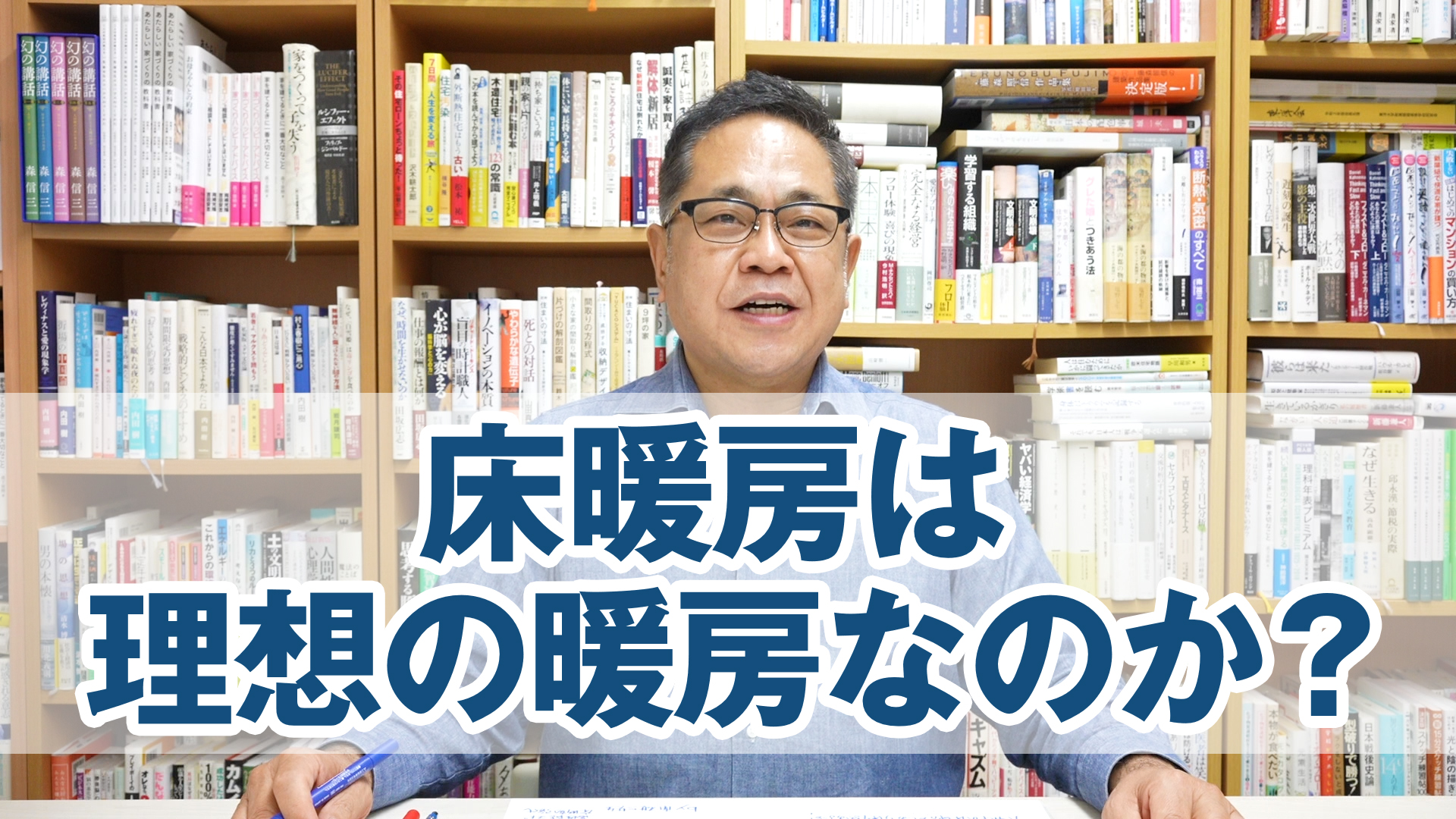2025年板「オール電化VSガス」どちらが良いか?を考える
今回は、2025年版「オール電化 vs ガス」どちらが良いかについて解説します。
このテーマはこれまでも多くの議論が交わされ、さまざまな意見がありますが、最近またこの質問を受ける機会がありました。せっかくなので、2025年の現時点で考えられるそれぞれのメリット・デメリットを踏まえ、どのような選択が最適なのか、私なりの考えを解説していきたいと思います。
まず、オール電化の定義について確認します。多くの方はご存じだと思いますが、家を建てた場合、家電や照明には必ず電気を使う必要があるので、電気はどの家庭でも不可欠です。そのうえで、それ以外のエネルギー消費として挙げられるのが「給湯」です。風呂釜でお湯を沸かすことや、お風呂全般に関連する設備、レンジやオーブンといった調理機器の使用が挙げられます。これらの用途に電気のみを使用するのが「オール電化」で、ガスを併用する場合は「ガスを使う家」という分類になります。
まずコストの面から考えると、初期費用はガスを使う方が安いです。一方で、給湯や調理にかかるランニングコストは、オール電化の方が有利と考えられています。なぜオール電化の方がランニングコストを抑えられるのかというと、一つの大きな理由は給湯にあります。住宅におけるエネルギー消費の中で、最も大きな割合を占めるのが給湯です。給湯のエネルギー消費量が大きい以上、それをできるだけ安くまかなう技術が重要になります。そこで活用されるのが「ヒートポンプ」という技術です。ヒートポンプは、空気中の熱を取り込み、電気1の力に対して何倍ものエネルギーを生み出せる仕組みになっています。
ルームエアコンも同じ技術を用いており、この技術を利用したのが「エコキュート」です。エコキュートは電気を使ってお湯を沸かすシステムですが、ガスを直接燃やしてお湯を沸かす方式よりも省エネ性能が高いとされています。これは現在の技術水準において定説となっており、結果としてオール電化の方がトータルコストを抑えやすいという考え方が主流です。私自身も、こうした技術の優位性を踏まえ、オール電化の方が経済的に有利だと判断しています。
一方で、安全性の観点から考えると、「ガスを使うと直火なので、お年寄りや子どもが引火しやすかったり、吹きこぼれによる火災のリスクがあるため、IHを使うオール電化の方が安全だ」と言われることがあります。しかし、最近ではガス器具の安全性も向上しており、メーカーもさまざまな対策を講じています。
ただ、私自身が特に感じるのは、IHの使いやすさの問題です。私の84歳の母の例を挙げると、親戚の家でIHを使おうとした際に操作が分からず、戸惑っていました。IHの操作自体は決して難しいわけではないのですが、長年ガスに慣れ親しんでいる方にとっては、使い慣れたものの方が安心できるという側面があります。したがって、現在住んでいる家をオール電化にする際には、本当にお年寄りがIHを問題なく使いこなせるのか、現実的に確認しておくことが大切だと思います。
また、安全性に関するもう一つの視点として、災害時のインフラ復旧スピードが挙げられます。例えば、東日本大震災では、電気の復旧は比較的早く、1週間ほどでほとんどの地域が復旧したのに対し、ガスは復旧に5週間ほどかかったというデータがあります。地域や状況によって異なりますが、「災害時の復旧の速さを考えると、電気の方が安心」と考える方もいます。
このように、経済性や安全性を考えるうえで、家族構成や住まい方によって有利・不利が変わってくることも重要なポイントです。例えば、共働きのご夫婦で昼間は家にいない家庭であれば、深夜割引を活用できるため、電気の方がやや有利になることが多いです。一方で、2世帯・3世帯のように、おじいちゃん・おばあちゃん、息子夫婦、さらには孫・ひ孫までいる家庭では、日中に電気を使う時間が長くなるため、場合によってはガスの方が経済的になることもあります。
したがって、「絶対にこちらが得」と言い切るのではなく、家族構成や住まい方によって最適な選択肢が変わることを理解しておくことが大切です。
また、調理に関しても一長一短があります。IHの場合、使用できる鍋が限定されるため、IH対応の調理器具を揃える必要があります。さらに、「ガスのようにダイナミックに鍋を振る炒め物がしにくい」と感じる方もいます。そのため、調理方法にこだわりがある方や、現在の調理器具をそのまま使いたい方にとっては、ガスの方が適している場合もあります。一方で、ガスは燃焼するために酸素を消費しますが、IHは空気を汚しにくいという利点があります。また、掃除のしやすさという点では、IHの方が表面がフラットなため、拭き掃除が簡単です。最近ではガスコンロも「ガラストップ」のものが増え、掃除のしやすさが向上していますが、五徳があるため、IHに比べると手間がかかることもあります。このように、使う人の好みや生活スタイルによって、どちらが適しているかが変わってきます。
給湯器については、エコキュートの省エネ性能が高いことは間違いありません。ただし、エコキュートを好まない方の中には、湯切れが気になるという声があります。貯湯槽にお湯を溜める方式なので、お客様が来て大勢でお風呂に入ると、お湯が足りなくなってしまうことがあります。しかし、最近のエコキュートはこの課題に対応した機種も登場しており、技術の進化によって弱点を克服しつつあります。一方で、ガス給湯器は比較的安価な製品が多く、初期費用の面ではエコキュートよりも安価というメリットがあります。ただ、近年はエコキュート導入に対する補助金も用意されているため、コスト面でも互角に近づいてきています。このような背景を踏まえ、どちらを選ぶかは、単なる価格の違いだけでなく、家庭の使い方によって考えることが大切です。
例えば、シニアのご夫婦がエコキュートの導入を検討する際に、「お湯を大量に使うことがなく、シャワーで済ませることが多いから、ガスの方が安い」と考える方もいます。このような場合、ガス給湯器の方が経済的になることも十分に考えられます。逆に、私自身は職人の家庭で育ち、「湯船にしっかり浸かりたい」というタイプなので、ある程度の湯量が確保できることを重視します。このように、給湯の選択についても、それぞれの家庭の生活スタイルや好みによって適したものが異なります。
ここまでの話を踏まえたうえで、なぜ2025年の今、このテーマを取り上げたのかについてお話しします。それは、国が今後推進しようとしている住宅の方向性が関係しています。具体的には、「ZEH(ゼロエネルギーハウス)」や「GX志向型住宅」といった基準を重視する流れが強まっているからです。
ZEHとは、住宅のエネルギー収支を実質0にすることを目指した住宅のことで、GX志向型住宅は、それをさらに進め、よりエネルギー消費を抑えた住宅を指します。これらの住宅では、太陽光発電の設置がほぼ前提となっており、エネルギーの「自家消費」を積極的に進めることが求められています。これまでの太陽光発電は、発電した電気を売電し、その収益で電気代を相殺するという考え方が主流でした。しかし、現在は売電よりも「発電した電気を自宅で使う」ことに重きを置く流れになっています。
この流れの中で、エコキュートも「ソーラーチャージモード」や「おひさまエコキュート」といった新しい機能を備えたものが登場しています。これは、太陽光発電で電気を作っている時間帯にお湯を沸かし、そのまま保温して使うという仕組みです。従来のエコキュートは、深夜電力を活用してお湯を作る方式が主流でしたが、現在は昼間の発電時間帯にお湯を沸かして、それを効率よく使う考え方に変わってきています。この仕組みを利用すると、太陽光発電の電気を無駄なく使うことができるため、エネルギーのロスが少なくなります。
今後の住宅は「自家発電した電気を、より効率的に使うこと」が重要なポイントになってきます。給湯器の選び方も、オール電化とガスの比較だけではなく、国の施策を踏まえたうえで考えることが求められる時代になってきています。
そして今年の後半以降、FIT(固定価格買取制度)に大きな改正が予定されています。従来は、発電した電力を10年間固定価格で買い取る仕組みでしたが、新制度では最初の4年間は少し高めに買い取る形に変更される予定です。この改正により、太陽光発電の導入がしやすくなり、できるだけ早く投資回収ができるように促進されます。これも住宅のエネルギー選択において重要なポイントになります。この新しい制度に乗るのであれば、オール電化との相性は非常に良いと考えられます。そのためには、建物自体の高気密・高断熱性能も重要になってきます。住宅はトータルで省エネ性能を高めることが重要です。
特に、日本の夏は年々厳しく暑さが長期間続くため、冷房の効率化が不可欠です。共働きの家庭では日中は家を空けていても、帰宅後から就寝までの時間にしっかり冷房を使う必要があります。また、日中に在宅するシニア世帯では、一日を通して快適な室内環境を維持しなければ、熱中症のリスクも高まります。これらを踏まえると、全館空調などを導入し、エネルギー効率の良い形で室内環境を整えることが求められます。
さらに、日本の住宅における冬の捉え方も変わってきています。これまでは、こたつや電気ストーブで局所的に暖を取るスタイルが主流でしたが、最近では住宅全体を暖かくする考え方にシフトしつつあります。特に、洗面所やトイレ、寝室など、家のどこにいても快適な温度を保つことが重視されるようになりました。この観点からも、太陽光発電との組み合わせで省エネ性能を高めることは、理にかなっているといえます。
また、空調についてはエアコンを使うのが最も効率的です。最近のヒートポンプ技術を活用したエアコンは省エネ性能が非常に高く、快適性を維持しながらエネルギー消費を抑えることができます。そのため、新築やリフォームを検討する際は、エネルギー効率の高い設備を取り入れることが重要になります。
既存の住宅について考える場合、高性能な断熱・気密性を確保するリノベーションが難しいケースもあります。その場合、現状の住宅性能を踏まえた最適な暖房手段を選ぶ必要があります。特に寒冷地では、十分な暖房能力を確保することが重要になるため、ガスや石油のファンヒーターを併用するのも一つの選択肢です。何よりも、住む人の健康を守り、快適に暮らせる環境を整えることが最優先です。
しかし、新築やリフォームによって住宅の性能向上が可能な場合は、オール電化と太陽光発電を組み合わせることで、よりエネルギー効率の良い住宅を実現できます。これが、私自身が現時点で考える「最適な住宅のあり方」です。あくまで一つの情報として参考にしていただければと思います。
また、オール電化を基本にしつつ、LPガスを併用する選択肢もあります。例えば、調理はガスを使いたい、乾燥機はガス式の「乾太くん」を使いたい場合、LPガスを導入することで対応できます。LPガスは災害時に使用できるメリットがあります。そのため、災害対策の観点からもガスとの組み合わせを検討するのは有効な選択肢の一つです。
住宅のエネルギー選択は、オール電化かガスという二択ではなく、住宅全体の性能やライフスタイル、将来のエネルギー政策を見据えて考えることが重要です。それぞれの家庭に合った最適な選択をしていただければと思います。ぜひ参考にしてください。