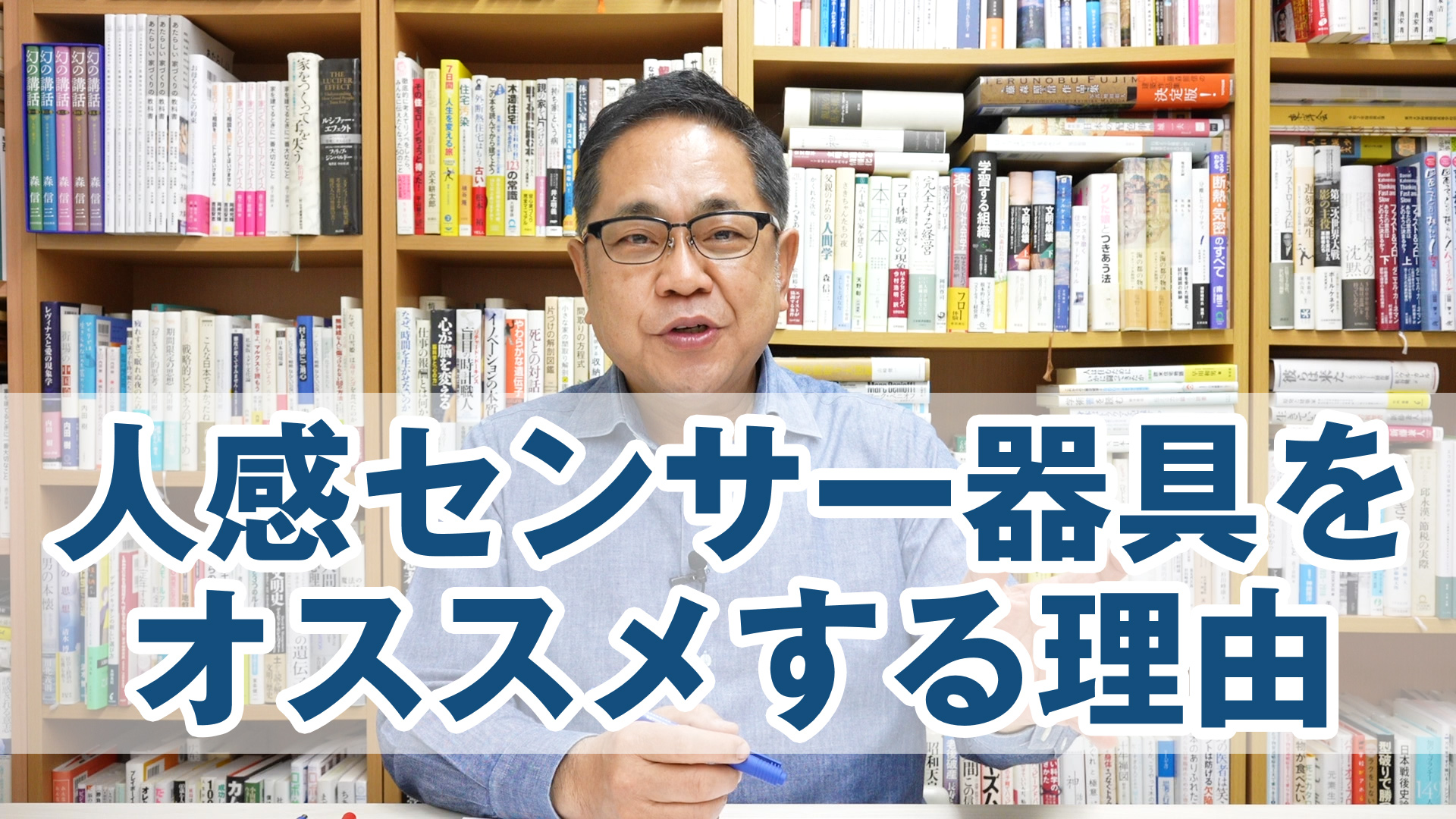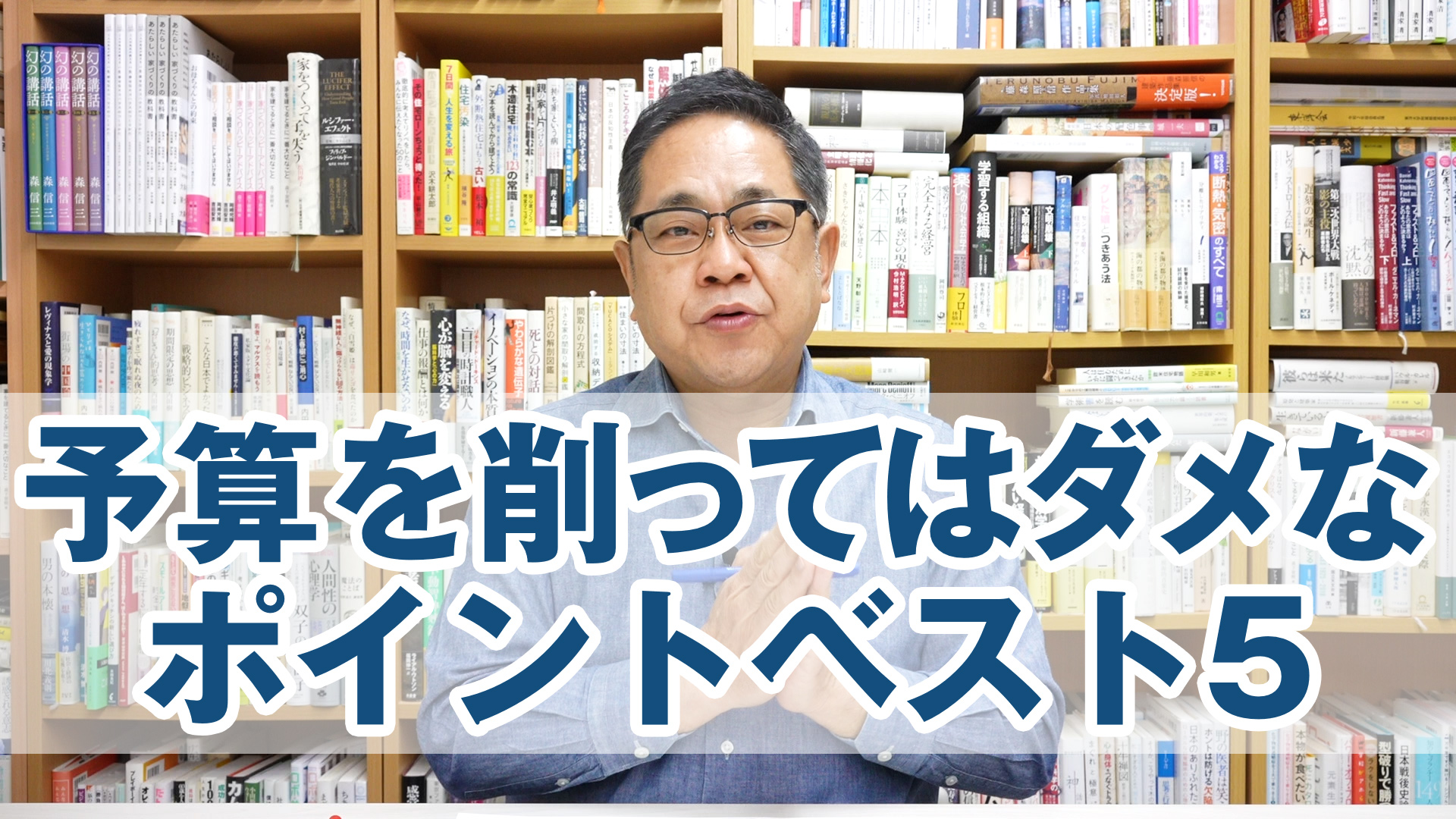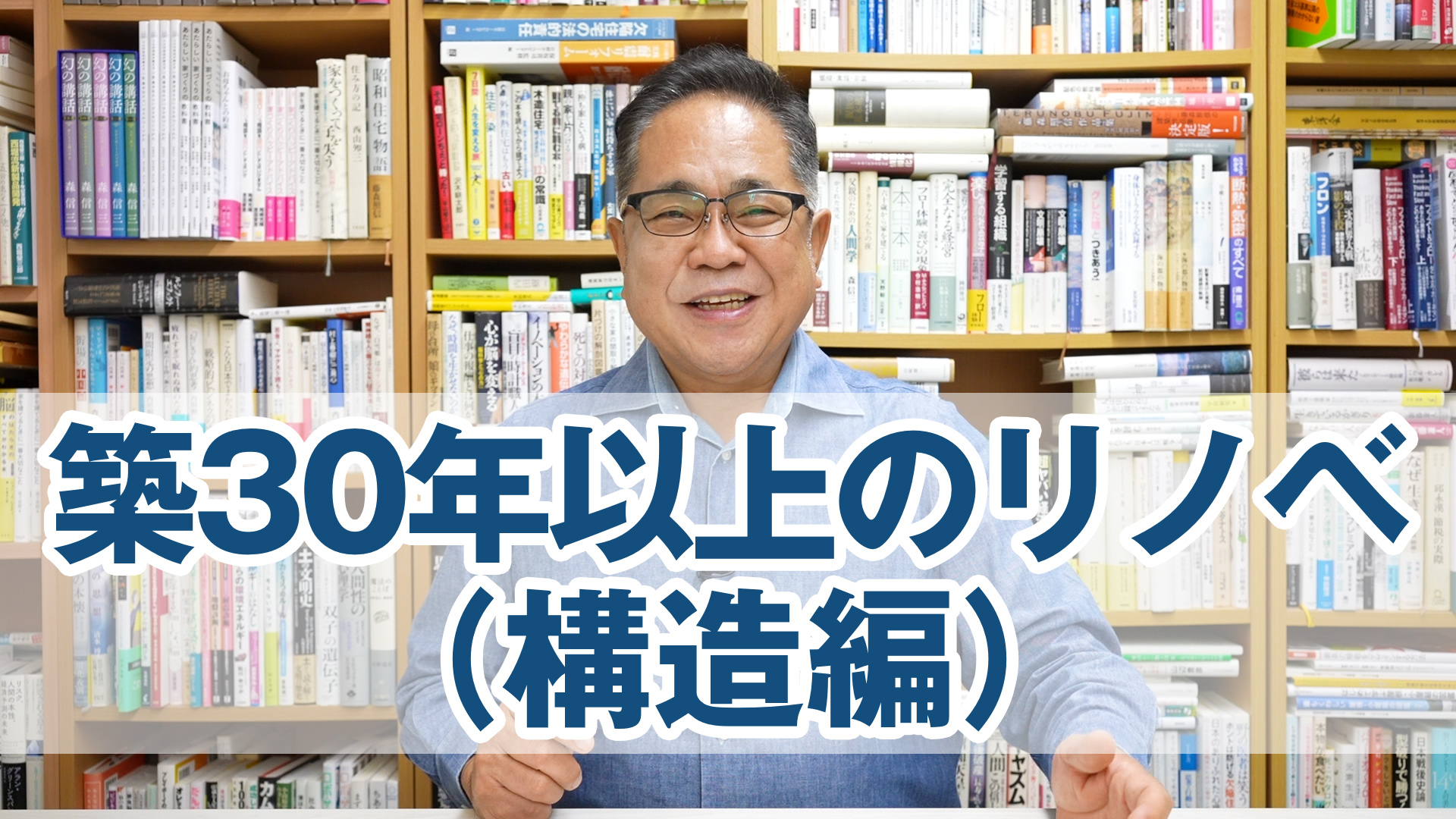間取りの新常識:準コートハウスはたのしい!
今日は「間取りの新常識シリーズ」ではありませんが、最近ご希望される方が増えている“コートハウス”、その中でも“準コートハウス”という考え方についてお話ししたいと思います。
「センターコートのある家」や「中庭のある家」といった言葉を耳にされたことがある方も多いと思います。こうしたコートハウスは、とても人気がありますし、もちろん素敵なんですが、少し視点を変えると、より経済的に実現できるという面もあります。今回はそのあたりについて解説していきます。
この話は、例によって僕の受け売りなんですが、『家づくりのすごい新常識』という本の中で、設計士の杉浦光さんが語っておられた内容をもとにしています。これは確かに、皆さんが知っておかれると役に立つと思いましたので、ご紹介します。
まず、コートハウスとはどんな家かというと、建物を上から見たときにコの字型になっていて、へこんだ部分に庭やデッキを設けるという構成になっています。
この形の家がなぜ人気なのかと言うと、都市部に近いエリアでは隣家や道路との距離が近く、外に庭があっても視線が気になってくつろげないことが多いからです。たとえば僕は、家の前のウッドデッキでTシャツとショートパンツ姿でビールを飲むくらい平気ですが、うちの女房は「すぐ前が道路やん」と言って絶対にやりません。
こうした視線を気にせず過ごせる空間が、コートハウスの大きな利点です。
僕がよく言う「中間領域」――外でも中でもない、そのどちらともつかない豊かな空間――があると、家はグッと豊かになります。コートハウスはまさに、この中間領域を実現しやすい家のかたちです。
ただし、こうした構造にすると、同じ床面積でも外壁や開口部が増えるぶん、どうしても建築コストが割高になります。
もう一つの課題は、日射の取り込みです。僕は冬場の太陽の熱をしっかり取り込む“パッシブ設計”に強いこだわりを持っているのですが、コの字型だと朝の東日や夕方の西日が入りづらくなります。南中する時間帯(およそ11時~14時)には日が入っても、それ以外の時間帯では、建物の形状によって日差しが遮られてしまうこともあります。建物の高さや窓の設け方を工夫すれば解決できますが、少し設計に工夫が必要になります。
また、別の動画でも紹介したことがありますが、著名な建築家・レーモンド夫妻が住まれていた家には、建物の中に中庭的なスペースが設けられており、そこがいつも食事の場になっていたそうです。とても素敵ですよね。
ただ、杉浦さんが言うには、それは良いとしてもコスト面でのハードルがある、ということでした。そこで紹介されていたのが「準コートハウス」という考え方です。
「準コートハウス」はコの字型ではなく、L字型にして東南の角を少し切り取るようなイメージで、そこにスペース(中庭)をつくります。さらに、その外側に“袖壁”を建てることで視線を遮ります。袖壁は構造体ではなく、外構の一部として設けられるため、コストを抑えることができます。
杉浦さんの試算によると、ざっくりではありますが、通常のコートハウスよりも40万〜150万円ほど安くできるそうです。5〜60万円違うだけでも、そのぶんキッチンや窓のグレードアップに充てられますよね。
この形であれば、東からの陽も入りますし、長い時間にわたって日射を得ることができ、プライバシーもしっかり守られるという利点があります。コートハウスと同じような機能を果たしてくれるわけです。
一方で、壁を設けなければ「オープンデッキ」になります。それはそれでコストはかかりませんが、プライバシー性には劣ります。
たった一枚の壁を加えるだけで、コートハウス的な中間領域を実現できるなら、準コートハウスはとても面白い選択肢になると思います。
杉浦さんが例として挙げておられたプランでは、LDKやダイニング、畳コーナー、階段まで含んで8畳、6畳、6畳とコンパクトに構成されながらも、しっかりと外とのつながりが考えられています。
この袖壁の設け方次第で、外からの視線を完全にカットすることができるのも大きなポイントです。たとえば道路に面していても、塀の配置を工夫すれば、来客が自然と奥へと誘導されるような設計にすることも可能です。
僕の妄想ではありますが、たとえば近所の北尾さんがふらっと来て、「あ、森下さん、もう飲んでるの?」みたいな感じで、そのまま一緒にビールを飲む…そんな楽しい付き合いもできるかもしれません。
このように、袖壁や外構をうまく活用すれば、そこまでコストをかけずにコートハウス的な空間を手に入れることができます。
もちろん、都市部などで敷地いっぱいに建てる場合は、光の取り入れ方に十分配慮しないと、暗い家になってしまうこともありますので、注意が必要です。
ぜひ、間取りの新常識のひとつとして「準コートハウス」という考え方を取り入れてみてください。