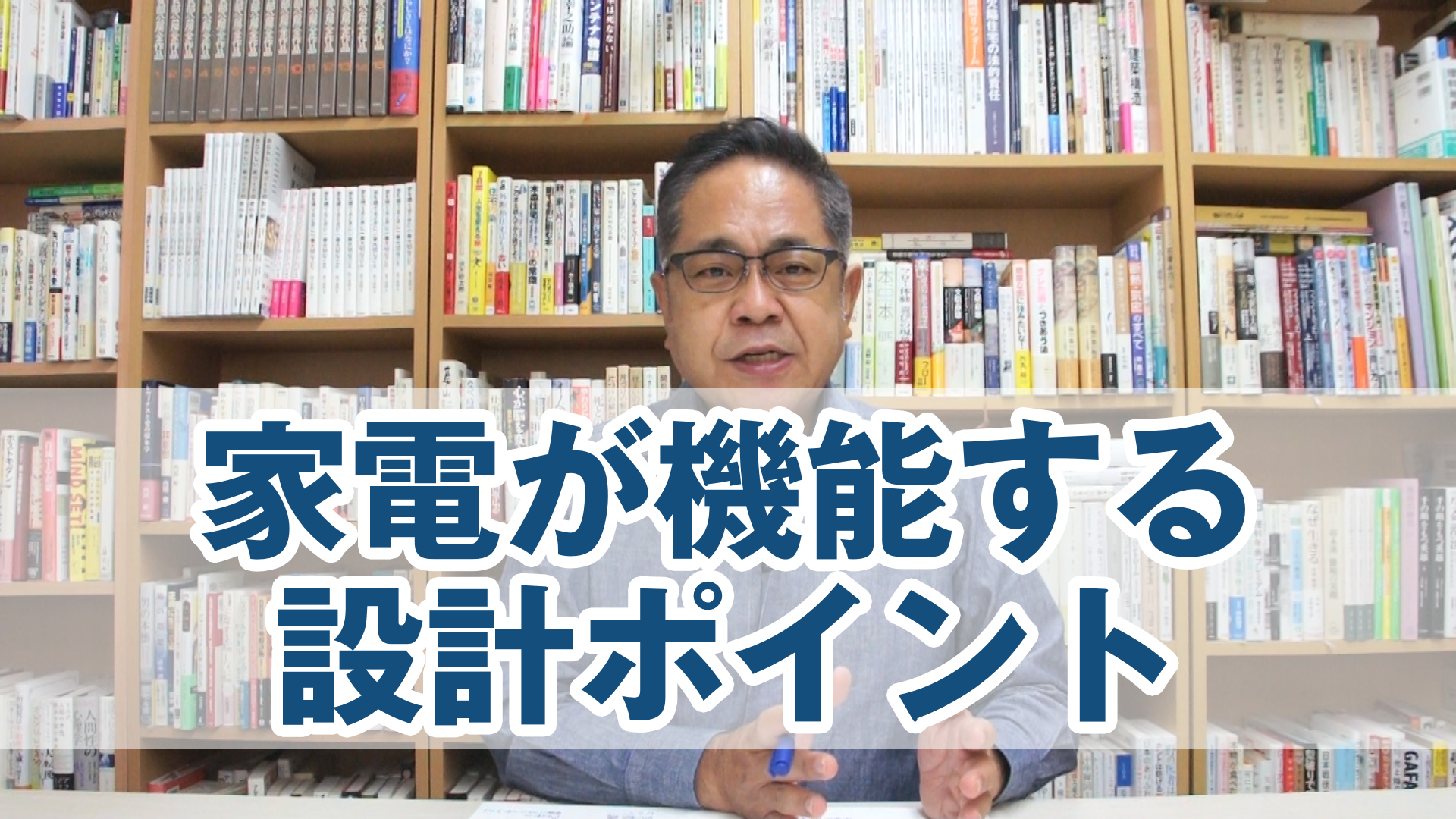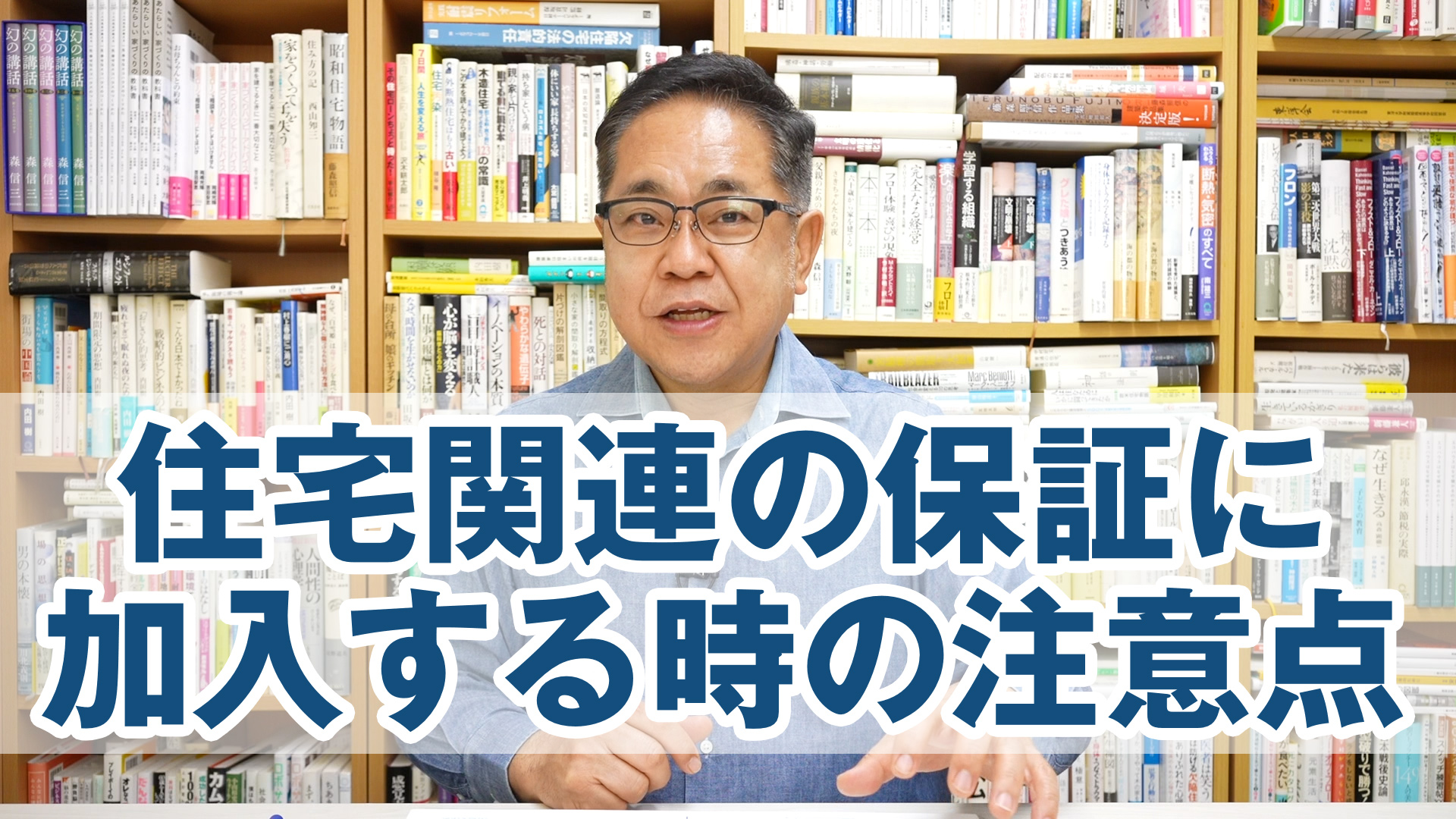木製フェンスの設置のあれこれ
今回は家づくりの中で「外構も並行して考えた方がいい」といつもお話ししている中で、最近人気のある木製フェンスについて、設置時のポイントなどを解説していきます。
これまでエクステリアといえばアルミや樹脂が主流で、20〜30年ほど人気がありましたが、最近は“原点回帰”的に木製の塀やフェンスの良さが見直されていて、注目が集まっています。
木製フェンスには多様なバリエーションがありますが、大きく分けて「横格子フェンス」「縦格子」「パネル型フェンス」の3つのスタイルに分類できると思います。いずれも、支柱が必要になりますが、その素材も木・アルミ・スチールなど選択肢があります。軽快感を出したいならスチール、統一感を持たせたいなら木製、腐食が心配な場合はアルミというように、用途や美観に応じて選べます。
格子フェンスでは、板と板の“間隔”が非常に重要になります。完全に目隠しをしたい人もいれば、風や光を少し通したい人もいて、好みのグラデーションがあります。横格子なら、等間隔に並べるだけでなく、板の幅を太・中・細で変えてリズムを出すパターンもあり、特に建物の正面などでは見栄えを意識した配置が効果的です。
縦格子では、縦に板を並べるだけでなく、固定するための横桟が必要になるため、施工がやや複雑になります。これも板の間隔で見え方が大きく変わります。
視線は遮りたいけど風は通したいという場合、「互い違い張り」という方法があります。支柱の両側に交互に板を張ることで、真正面からは隙間が見えず視線はカットできますが、風は抜けるという優れた構造です。最近では、S字状に曲げて連続させた互い違いフェンスも人気で、見た目の柔らかさも相まって注目されています。
互い違い張りのメリットは、裏表がなくなる点にもあります。通常のフェンスだと、道路側が表で、家側からは裏側が見える構造になりますが、互い違いだと両面ともに美しく見えるため、家の内外どちらから見ても違和感がありません。
「パネル型フェンス」は、既製品のラチスパネルやルーバー格子を使ったスタイルで、ホームセンターでもよく見かけます。ラチスパネルは取り替えがしやすく、DIY的な手軽さもありますが、材寸が小さく強度に劣るものもあるため、支柱の間にしっかり“頭繋ぎ”を入れて補強することが大切です。レッドシダーなどの材が使われることが多く、防腐塗料をしっかり塗る、取り替えを前提に設計するなど、耐久性に配慮が必要です。
木製フェンスの印象は、使い方やデザインで大きく変わります。細かな格子で間隔を狭めれば和風に、太めの板を白く塗れば西洋風になります。塗装も、ベタ塗りより木目を活かしたオイル系の仕上げの方が耐久性が高く、おすすめです。
支柱の施工にも注意が必要です。僕は「フェンスブロック」という、コンクリート製で中央が空洞になったブロックをよく使います。これに柱を差し込んで、モルタルで隙間を埋めると安定感が増します。地面に埋まる“根入れ”部分は、支柱全体の1/3程度(例:高さ3mなら1m)を確保した方が良いです。これをケチると傾いたり倒れたりしやすく、境界トラブルの原因にもなりかねません。
耐久性の高い木材として「セランガン・バツ」や「ウリン」のような油分を多く含んだ木材を、そのまま地面に埋めて使う方もいますが、個人的にはできればコンクリートなどで木と土を絶縁した方が、より長持ちすると思います。
RC擁壁の上に設置する場合は、アルミやスチール製の“柱脚”をアンカーで固定し、その上にヒノキなどを使ってフェンスを組むことも可能です。このときも、柱の上に“頭繋ぎ”として厚めの笠木を渡すと、強度が増します。笠木には雨水が溜まりやすいため、耐久性のある材を使うか、金属板で被せて片流れの勾配を取るなどの工夫をするのが長持ちのコツです。
木製フェンスは、アルミ製よりも植栽と馴染みやすく、見え方の自然さが全然違います。設計や施工に少し手間はかかりますが、その分“味”のある空間が生まれます。ぜひ挑戦してみてください。